奈良とローマ
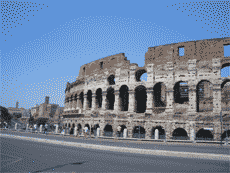
数年前に当時教養科目に存在した「比較文明史」という授業を担当したときに、「中世のローマと奈良」というテーマを選んだ。
このタイトルをいうと、たいていの研究者仲間は訝しそうな顔をした。「奈良とローマ?なぜこの二つを並べるのか。どうせ比べるなら、長安ではないのか。(これは西洋史を専門とする私には無理な話である。)それに奈良といえば、なんと言っても奈良時代だろう。ローマもまた、なんと言っても古代ローマ帝国の話だろう。なぜ中世なのだ」
当然の疑問である。
それに対して、次のように、いいわけがましい説明をした。
奈良もローマもどちらも古代においては、都だったが、その後都の地位をすべりおちて、衰退したとされる。しかし、実際には、中世にはどちらも宗教上で特筆すべき位置にあり、それゆえに巡礼者にせよ、教えを学ぼうとする者にせよ多くの人々をひきつけ、特異な「門前町」として生き続けることになった。古代の都がしばしばただの「遺跡」としてしか残らなかったのに対して、中世に宗教都市として発展を見せたことが現在につながったという意味で共通性がある。だから、この二つを比較してみることはおもしろいのではないかと思うと。ついでにいえば、奈良とローマは姉妹都市なので、どっちも知っておくのはいいのではないかと。
実際に、いい授業ができたかといえば、その自信はない。ただ、印象深かったのは、「大学の授業で一人の歴史の先生が、日本史も世界史も語るのを初めて聞いた」という感想である。今は、高校の歴史では日本史と世界史に分かれ、それぞれでスペシャリストが話すことが多く、生徒もまた入試を考えてどちらかしか履修しないことが多いようである。大学という場で、高度な専門性が強く求められるにもかかわらず、こんな授業をしようとしたのは、やはり無謀だったのかもしれない。ただ、私にとっては、従来とは違った目で物事をみてみるいい機会だった。
(山辺規子 やまべ・のりこ 中世ヨーロッパ史)