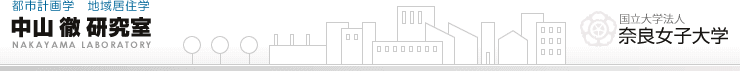
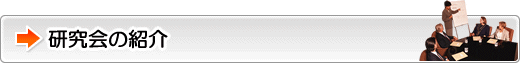 各種研究会の案内 以下の研究会は中山が主幹、参加している研究会です。公開されていますので参加を希望される方は、中山までお問い合わせください。 1.保育行財政研究会 2.生活支援システム研究会 3.幼保総合施設研究会 4.学童保育研究会 5.中国・内モンゴル研究会 6.中国・子ども研究会 7.中国・高齢者研究会
研究会の目的 保育制度改革が進んでいますが、その内容は必ずしも望ましいものではありません。この研究会では、今、進んでいる保育制度改革をどう評価すべきか、それにどう対応すべきか、望ましい保育制度とは何か、を情勢の変化に対応しながら検討しています。 研究会のメンバーは、大学教官、保育関係者、自治体関係者、大学院生などです。常時研究会に参加しているメンバーは数名程度です。研究会は、大阪保育研究所会議室で開催しています。 この研究会の目的は、公的保育制度を発展させることです。具体的には、情勢の節目ごとに、保育関係者、保護者、市民向けに、制度改革の問題点を解明し、運動の方向性を示すための本を書くことです。この研究会に参加を希望される方は、研究会が今までにまとめた本を一読し、趣旨に賛同できるかどうかを判断した上で、中山までご連絡ください。 保育行財政研究会の出版物 (1)「公立保育所の民営化、どこが問題か」自治体研究社、2000年1月、全97p (2)「保育市場化のゆくえーアメリカ保育調査報告ー」 自治体研究社、2001年2月、全59p (3)「保育市場化のゆくえーアメリカ保育調査報告ー(資料編)」自治体研究社、 2001年2月、 全109p (4)「保育所への企業参入、どこが問題か」自治体研究社、2001年4月、全124p (5)「市場化と保育所の未来」自治体研究社、2002年8月、全181p (6)「保育所の第三者評価、どこが問題か」自治体研究社、2003年2月、全92p (7)「幼保一元化ー現状と課題ー」自治体研究社、2004年2月、全123p 現在の研究テーマ 公立保育所の民営化・民間委託について 指定管理者制度、地方独立行政法人法、公立保育所運営費の一般財源化等々で、公立保育所を巡る状況が大きく変化しています。その一方で、民営化に対して保護者が裁判を起こすなど、民営化・民間委託をめぐる動きは、重大な局面を迎えています。本研究会は、2000年に「公立保育所の民営化ーどこが問題かー」を出版しましたが、その後の情勢を踏まえ検討を進めるものです。
研究会の目的 日本は高齢化、少子化が同時進行しています。この研究会では、時々の状況に合わせて、高齢化、少子化とテーマとして、研究に取り組んでいます。現在、重点を置いているのは小学生の放課後を地域社会でどのように保障すべきかです。 研究会のメンバーは、大学教官、建築家、大学院生などで、常時研究会に参加しているメンバーは10名程度です。研究会は、京都の華頂短期大学で、月1回程度、開催しています。 主な研究業績 (1)「これからの配食サービス」かもがわ出版、2004年10月 (2)『社会福祉協議会による毎日型配食サービスに関する調査 −高齢者の食関連サービスのあり方に関する研究−』 2004年11月、「日本家政学会誌Vol.55、NO.11」p885〜p894 (3)『オーストラリアにおける配食サービスについて』 2004年11月、「日本家政学会誌Vol.55、NO.11」p895〜p902 (4)『地方自治体における高齢者福祉施設の配置計画』 2005年12月、「日本建築学会技術報告集第22号」p445〜p450 (5)『社会福祉協議会による毎日型配食サービスの地域別検討と類型化 −高齢者の食関連サービスのあり方に関する研究−(第2報)』 2006年4月、「日本家政学会誌Vol.57、No.4」p51〜p59 (6)『介護サービス基盤の圏域設置計画とその整備手法 −地方自治体における高齢者福祉施設の配置計画その2−』 2006年12月、「日本建築学会技術報告集第24号」p381〜p386 (7)『介護サービス基盤における日常生活圏域に関する研究 −平成17年度地域介護・福祉空間整備等交付金(市町村交付金)の分析より−』 2007年4月、「都市計画論文集、No.42-1」pp81−86 現在の研究テーマ (1)小学生の放課後を地域社会でどのように保障すべきか、学童保育、全児童対策、児童館、公民館などのかかわりを検討しています。 (2)海外では、スウェーデン、カナダに焦点を当て、実態把握を進めています。
研究会の目的 2005年度から幼稚園と保育所を一体化した認定こども園がスタートしました。認定こども園は公的保育制度という点から見ると多くの問題点を抱えています。認定こども園がどのような問題を抱えているのか、幼保一元化を進める場合、どのような点に注意して進めるべきかを検討しています。 研究会は、大阪保育研究所(大阪市内)で、概ね月に1回の割合で進めています。参加しているメンバーは、大学教員、保育関係者、大学院生などです。 主な研究業績 (1)「幼保一元化と認定こども園」かもがわ出版、2006年9月 (2)『幼保総合施設の全国的現状調査』2006年9月 「日本家政学会誌Vol.57、No.9」p23〜p32 現在の研究テーマ (1)認定こども園の実態 2006年度に出版した「幼保一元化と認定こども園」で認定こども園の制度的な問題点は、ほぼ把握できました。今後は、認定こども園が実際どのように進んでいるのかを調査します。具体的には、設置・運営主体、保育料、職員体制、カリキュラムなどです。 (2)幼保一元化のあり方について 認定こども園について調査すると同時に、幼保一元化のあり方についても検討します。具体的には、(1)の調査と並行して進めます。
研究会の目的 2007年度から放課後子どもプランがスタートしました。これは学童保育と全児童対策を一体的もしくは連携して進めるものです。お互いに連携するのは望ましいことですが、地域によっては学童保育が全児童対策に吸収され出しています。 この研究会では学童保育と全児童対策のあり方、子どもたちの放課後の過ごし方について検討します。 研究会のメンバーは、大学教官、保育関係者、自治体関係者、大学院生などです。常時研究会に参加しているメンバーは8名程度です。研究会は、大阪保育研究所会議室で開催しています。 主な研究業績 (1)「放課後子どもプランと学童保育」自治体研究社、2007年11月、全139頁 現在の研究テーマ (1)学童保育と全児童対策の連携について 2007年に出版した「放課後子どもプラント学童保育」で両事業の一体化についてはほぼ把握できました。今後は、両事業の連携について調査・検討します。 (2)子どもたちの放課後について 放課後子どもプランの実施場所は小学校です。 しかし、地域には児童館、図書館、公民館、公園など、子どもたちが過ごせる場所がたくさんあります。地域全体で豊かな子どもたちの放課後をどのように作るべきかを検討します。
研究会の目的 中国・内モンゴル自治区を対象に以下、二つの視点で調査を進めています。一つ目は、草原地域における住宅の変化過程の把握です。内モンゴル・草原地帯の伝統的な家屋はゲルでしたが、最近ではほとんど消滅し、固定家屋に変化しています。ただ、固定家屋には地域差などが見られますが、その全容は明らかにされていません。これらのゲル、固定家屋がどのような理由で、どのように変化してきたかを把握します。二つ目は、草原の敷地割と、牧畜、住宅形態の関係です。 この研究は、奈良女子大学と中国内蒙古大学の共同研究で進めます。 主な研究業績 (1)「定住生活における移動住居ゲルの利用実態と用途変化 −中国・内モンゴル自治区シリンゴル盟の牧畜民を事例として−』 2008年8月、「日本建築学会計画系論文集No.630」p1735〜p1743
研究会の目的 中国では都市化、近代化が急速に進んでいますが、子どもを取り巻く諸条件の整備は必ずしもその変化に対応して進んでいません。そのためいろいろな問題が生じています。本研究会では、下記の三点にポイントを当て検討を進めます。一点目は、農民工の子どもたちの教育・生活問題です。上海を対象に、農民工の子どもたちの学校、生活環境を把握し、今後のあり方を検討します。二点目は、年少から都市部に出る子どもたちの問題です。中国の農村部では十分な教育を受けることができないため、小学校入学と同時に、親元を離れて都市部で暮らす子どもが増えています。それらの問題をどのように考えるべきかを、中国内モンゴル自治区を対象に考えます。三点目は、子どもの安全です。特に中国南部では子どもが犯罪に巻き込まれるケースが増えています。子どもの安全について検討します。 一つ目のテーマは上海理工大学、二つ目のテーマは内モンゴル女子幹部学校と共同で進めます。 主な研究業績 (1)「中国・内モンゴル自治区における「逆留守子ども」の生活実態に関する研究 −シリンゴル盟の東ウジュムチン旗を事例として−」 2008年12月、「子ども環境学研究Vol4、No3」48頁〜55頁
|