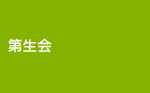第2回 第生会卒業設計賞
田中 麻美子
「Historical Station Front」
講評
観光目的で奈良を訪れた人々だけではなく、日常的な通勤通学などの目的で近鉄奈良駅を利用する人々もまた、この駅の空間に対するなにがしかの物足りなさや貧しさを感じているのではないでしょうか。この作品は、奈良を訪れる人と奈良市民に長らく共有されてきたこの感覚の解消と、歴史的な市街地の玄関口となる新たな環境と景観の創造に正面から取り組んだものです。その特徴は、次の3点に集約されるでしょう。第一に、大和西大寺駅から平城宮跡を経て地下に入る間の一連のシークエンスの延長上に、駅における空間体験を位置づけていることです。乗車中と下車後の乗客の方向感覚を阻害することなく、奈良の歴史的環境の中心に誘導する空間計画、その間の高揚感の維持と増幅を意図した地下から地上へと連続するコンコースと大階段の空間造形が具体的な提案です。二点目は、交通広場やオフィスビル等、現在の地上部にあるすべての機能を損なうことなく維持することによって提案のリアリティを担保しつつ、プログラムと建築ボリューム、動線などの組み替えによって、魅力のある街並みの景観を創出するアーバンデザインやランドスケープデザインへの提案があることです。さらに三点目として、駅の南側に広がる歴史的市街地の空間構造を尊重しつつ、新たなオープンスペースを挿入することによって、商業空間の活性化と興福寺境内との空間的景観的な連続を意図していることがあげられます。最終的なプレゼンテーションに関しては、図面表現の密度や模型の精度なども学部の卒業設計としては高い水準にあるものと認められ、展示会における見せ方の工夫にも非凡なものを感じることができた作品です。(指導教官 宮城俊作)
第2回 第生会卒業論文賞
神戸 美音
「戸建住宅の雨戸に関する研究─住生活学の視点から─」
概要と講評
雨戸は日本の伝統的な木造住宅において、住宅の内と外の関係を調節するものとして存在してきた。しかし近年、ガラスやサッシなどの品質向上や人々の生活の変化など、種々の背景からその役割が軽視されつつある。
本研究は、このような状況にある雨戸に着目し、雨戸の物理的な建具としての役割だけでなく、現代の住生活における雨戸の新たな生活上の意味を見出すことを目的としている。
まず雨戸の全国的な統計資料により、雨戸の種類や設置率等の年次動向を把握し、つぎに建築家が設計した近年の注文住宅における現代の雨戸の動向を明らかにしている。それらを踏まえて、ニュータウンの戸建住宅居住者を対象とした質問紙調査を行い、雨戸の使い方の現状、居住者の雨戸に求める役割や雨戸に関わる生活の諸意識を明らかにしている。
住み手の意識と生活様態から、雨戸が建具として気候や屋外環境に対応し、防犯面において居住者に安心感を与えていること、さらに、生活のリズムを作り出し、近隣へのメッセージを発信しているなど、住み手の求める雨戸の役割と住生活における存在意義を指摘し、卒業論文として高く評価される。本論文は2004年日本建築学会優秀卒業論文賞を受賞し、ダブル受賞となった。(指導教官 今井範子)
萬田 典子
「室内窓際のアサガオ植生が及ぼす室内温熱環境への影響」
概要と講評
近年、省エネルギーに配慮した環境にやさしい住まい方が求められている。夏季の暑さに対応した住まい方のひとつに日射遮へいがある。上記の卒業研究は、ヘチマやアサガオなどの植生を利用した日射遮へい効果を温熱環境面から定量的に把握することを目的とした研究である。
実測は、本学E棟4階の南側にある共同研究室2室を対象とし、窓際にアサガオを植えたプランター6個を設置したアサガオ室及びブラインドを用いて日射遮へいしたブラインド室で行い、外気の温度・湿度、各室の室温・湿度・黒球温度及びアサガオの緑被率(緑葉が窓面を被った割合)を6月~10月に連続測定し、被験者による温熱環境の感覚的評価も行っている。
室内温熱環境は、7月にはアサガオ室の黒球温度が約1℃高いが、緑葉が増えるに伴い、その差は小さくなり、9月中旬に緑被率が90%になるとほぼ同じとなり、ブラインドと同等の日射遮へい効果があるとしている。また、被験者による雰囲気評価ではアサガオ室で高い評価であり、「情緒豊かな」「ゆったりとした」との評価が得られ、アサガオ室では室温が高いにも関わらず温熱的快適側の申告が多く、緑葉の心理的効果が大きいことを明らかにしている。
以上の成果は、植生による日射遮へいが暑熱緩和および雰囲気評価に効果があることを明らかにしており、夏季の暑熱緩和や省エネルギーのための学内や住まいでの取り組みに有用な資料を提供した卒業研究として高く評価される。(指導教官 磯田憲生)