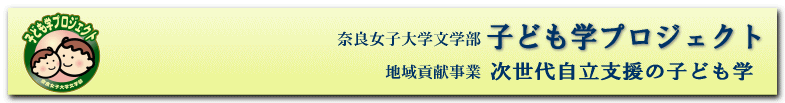
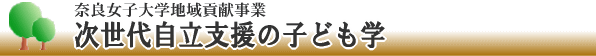 ■平成18年度実施報告 子どもの安全・保護と自立のはざま ――いま子どもたちの育ちはどうなっているのか 子どもをめぐる事件がマスコミを騒がせるなかで、子どもをもつ親や保育・教育関係者のあいだで 「子どもの安全保護」を求めるさまざまな対策が立てられています。 しかし、安全保護のみにこだわることでかえって子どもの自立を阻害しかねない現状もあります。 本企画では、家庭・学校・地域での子どもたちの安全と自立とを相互に折り合わせ、 子どもたちのよりよき育ちを展望するために、各回とも地域から情報提供をいただき、 正確な現状把握とともに、この現状に即応した理論と実践のありようを追求しました。 いま親が「子どもを守る」とはいったいどういうことなのでしょうか。 子どもが「親から巣立つ」とはいったいどういうことなのでしょうか。 全4回の講演会を通して、子どもたちの育ちの現況を見つめ、この問題をあらためて問い直しました。 一般 教員、児童福祉関係者、子育て支援関係者、青少年育成関係者、大学院生 ほか 講 師: 浜田 寿美男 (本学教授、附属幼稚園長) 情報提供:大澤 清 (奈良市教育委員会少年指導センター所長) 日 時:2006年10月22日(日)午後1時30分~4時 会 場: 奈良女子大学文学部南棟S218教室
講 師: 内田 良子(子ども相談室「モモの部屋」主宰、保健所心理相談員 (東京都)、NHKラジオ「子どもの心相談」アドバイザー) 情報提供:丹羽 眞佐子(大和郡山市教育委員会社会教育課社会教育指導員) 日 時: 2006年11月18日(土)午後1時30分~4時 会 場: 奈良女子大学 文学部南棟S218教室
講 師: 団 士郎 (立命館大学大学院教授・家族心理臨床家) 情報提供:三木 幸 (香芝市子育てサポートグループ Doula club) 日 時: 2006年 12月23日(土)午後1時30分~4時 会 場: 記念館2階 記念館講堂 (正門正面) 「子育ちの今と昔 ――このわずか50年で私たちは文明の大きな角を曲がった」 第Ⅰ部 講 演 講 師: 村瀬 学 (同志社女子大学教授) 演 題: 「新しい狼に出会う赤ずきんを考える」 【講演要旨】
第Ⅱ部 シンポジウム シンポジスト: 中村 美榮子 (奈良県教育研究所幼児教育指導監) 仲川 元庸 (奈良NPOセンター) 椙田 萬理子 (奈良女子大学附属小学校教諭) 日 時: 2007年2月17日(土) 午後1時~5時 会 場: 奈良女子大学 講堂 (東門北側)
子育ち・親育ちの臨床実践 昨今、幼児から子ども、青年まで、心と行動の組織化、体制化の問題は軸を見失ってきつつあります。 乳幼児段階での家庭における子育ての実際は、親と子どもの双方にとって、いわゆる各家庭閉鎖系ともいえる 空気の中で、普遍的確実感に裏づけられた関係性の体験を実現できていなくなってきています。 このことは、学童期以後になると、学校教育の担当者である教師と児童、生徒との間で互いに人間観や価値観を 共有できないまま、教育現場という閉鎖系の場の中で体験のひずみを経験することに移行してきています。 この企画では、こうした状況展開が子どもの育ちと親の育ちのどのような問題点につながってきているのかを 実践的観点から明らかにして、具体的にどのようなサポート関与が必要とされるのかという点にまで議論を 広げました。 同様に、学校教育現場の関係者とともに、教育現場に見られる子どもたちの問題事象をとりあげて、 教師と子どもがどのような関係性の再構築を展望できるのかについて議論しました。 一般、教員、保育関係者 ほか 日 時: 2006年 12月 2日(土)午後1時30分~3時30分 会 場: 奈良女子大学 生活環境学部会議室 日 時: 2006年 12月 9日(土)13時30分~15時30分 会 場: 奈良女子大学 生活環境学部会議室
保育における育ちと学びのかけはし 子どもの成長にとって園での育ちは、時間的(発達的)、空間的(場所的)な拡張性をいかにもっているのでしょうか。 本企画では、幼児教育において幼児の育ちとともに、どのように学びの礎が築かれているのか、就学後を見すえた 育ちと学びの連続性を中心に検討しました。 今年度は、文部科学省研究開発学校に指定されている2園から話題提供をいただきました。 幼小連携や保護者との連携、就学移行を視野に入れたカリキュラム・デザインなどについて、現状における課題と 困難をふまえた上で、子どもの育ちにいかなる保育活動が求められるのか議論しました。 幼児教育のこれまでの資産がどのように生かせるのか、保育の新たな意味と今後の展望を考えました。 保育関係者、小学校等の教員、幼児教育・初等教育等の行政・研究関係者、 学生、一般 ほか 話題提供: 奈良女子大学附属幼稚園 コメンテーター: 埋橋 玲子 (神戸女子大学教授) 日 時: 2006年 11月11日(土)午後1時~3時30分 会 場: 奈良女子大学 生活環境学部会議室 話題提供: 大和郡山市立治道幼稚園 コメンテーター: 成田 信子 (関西国際大学助教授) 日 時: 2007年 1月13日(土)午後1時分~3時30分 場 所: 奈良女子大学 生活環境学部会議室
|
|||||||||||||||
| Copyright(C)2006-2009 Project of "KODOMO-gaku" in Faculty of Letters, Nara Women's University. All Rights Reserved. | |||||||||||||||