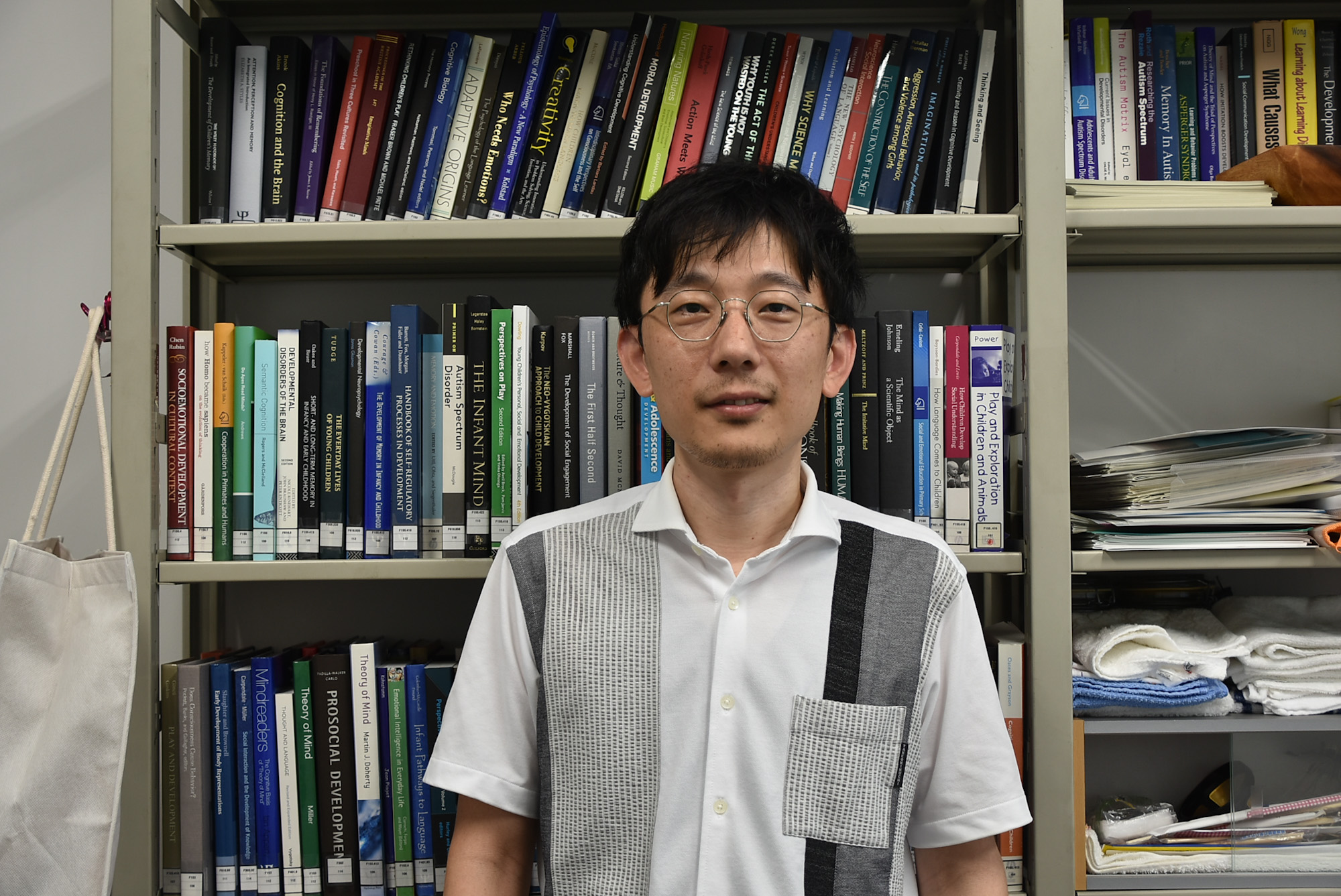自閉スペクトラム症児とコミュニケーション
~「こだわり」を活かす視点から~
【ならじょ Today41 号掲載】
狗巻 修司
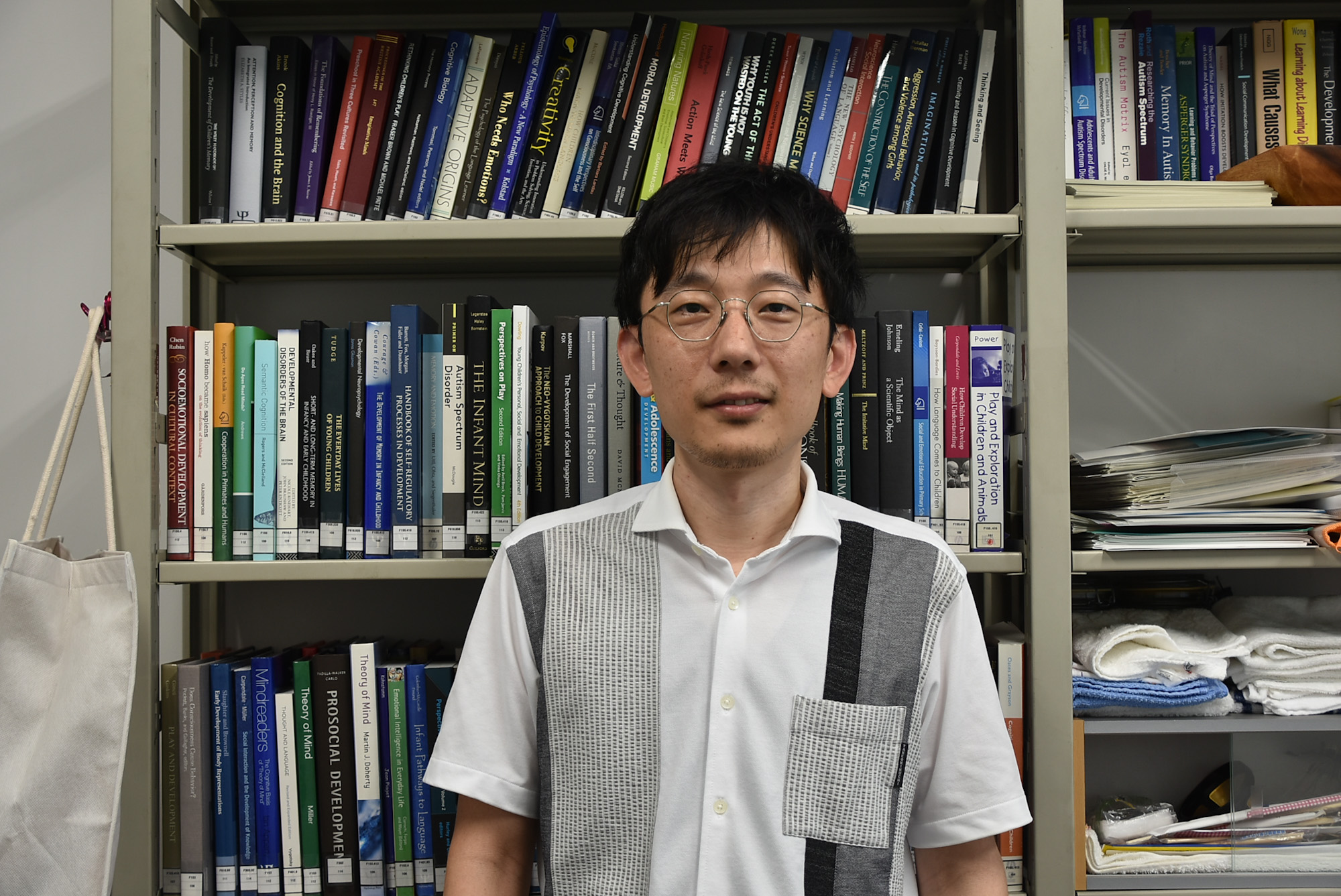
文学部 人間科学科 心理学コース
【研究テーマ】自閉スペクトラム症児のコミュニケーションスキルと反復的行動の発達的検討
【ならじょ Today41 号掲載】
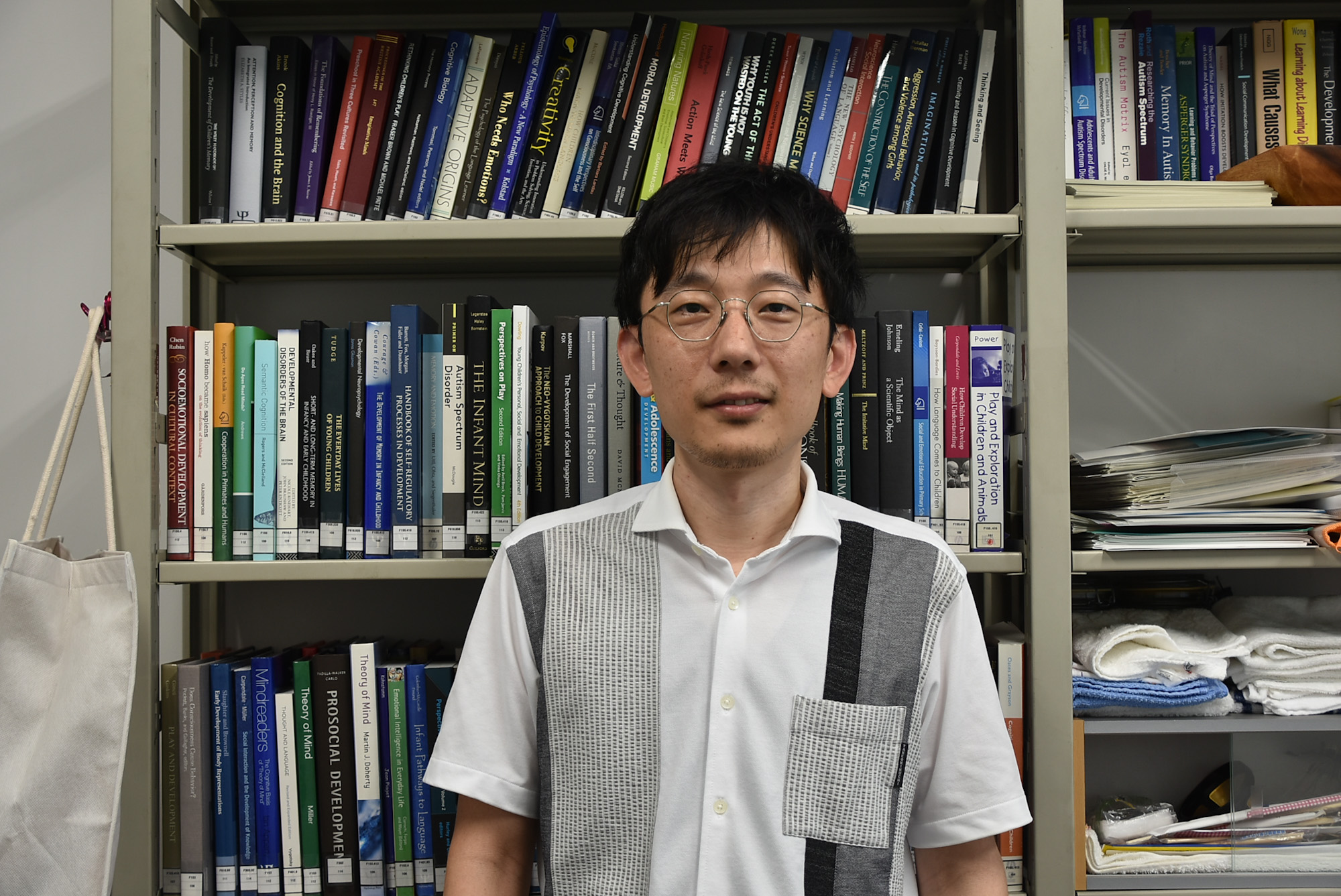
文学部 人間科学科 心理学コース
【研究テーマ】自閉スペクトラム症児のコミュニケーションスキルと反復的行動の発達的検討
―― 狗巻先生ご自身の研究内容について教えてください。(過去〜現在)
研究を始めたころから現在に至るまで、自閉スペクトラム症の子どもを対象に発達心理学の研究をしています。自閉スペクトラム症は対人関係においてその特性が顕在化するので、他者とのやりとりがどのように発達的に変化していくのかということを主に研究しています。 障害のある子どもも発達とともに変化していくものです。研究を始めたころは保育場面での観察が中心だったので、保育者と自閉スペクトラム症の子どもがどのように愛着関係を形成していくのかという研究や、自閉スペクトラム症の子どもたちとどうしたらやりとりがスムーズに進むのか、保育者との関係性を築いていくのか、といったいわゆる相互交渉(インタラクション)の研究をしていました。最近は自閉スペクトラム症の診断基準の1つである反復的行動、いわゆる「こだわり」と呼ばれる行動が相互交渉にどのような影響を与えているのかということについて研究しています。
―― そのような研究をされるようになったきっかけは何ですか。
きっかけは大学生のころにやっていたボランティアの活動です。もともとは乳幼児期の子どもの発達に興味があったのですが、障害のある子どもをキャンプに連れていくというボランティアがきっかけで障害のある子どもの発達に興味をもちました。
―― 担当授業やゼミでは,どのような授業や指導をされていますか。
授業は文学部の科目が中心です。座学は「発達心理学」の授業を担当しています。より専門的なものだと「障害者・障害児心理学」などの科目や、学部と大学院での実習関係の授業を担当しています。座学では「人間が生涯にわたってどのように発達していくのか」ということや、知的障害・身体障害・発達障害などをのある人たちの特性や発達的な変化から「障害っていったい何なのか」について扱っています。実習の科目は、学部生では見学実習が中心です。教育機関や福祉機関、医療機関などの施設に連れていくことや、オンラインで施設の職員様から話を聞かせてもらったりしています。大学院生ではより臨床的な実習を行います。障害のあるお子様に大学に来てもらい、プレイセラピーの実習を行なうとともに、実習の中で大学院生が学んでいることに対してスーパーバイズ※をしています。
ゼミは「発達心理学」系のゼミになるので、子どもの発達に興味をもっている学生がゼミに所属しています。学部では障害のある子どもたちを対象とした発達の研究をする学生もいますし、障害がない幼児期、学童期、なかには中高生の発達の研究をする学生もいます。大学院では、障害の有無によらず乳幼児期の子どもの研究をしている学生が多く、心理学的な実験や実験計画の立て方、観察の仕方、観察したことをどう分析していくのかということを指導しています。加えて、公認心理師の資格を取って現場で働きたいという学生も多いので、知能検査や発達検査の実施方法や検査結果をどう解釈するのかという基礎的な部分を、指導しています。(※これから取り組もうとする支援、または今取り組んでいる支援について、スーパーバイザーにアドバイス・指導をしてもらうこと。スーパーバイザーは学識経験者のため、発達支援を専門に研究をされている教授・准教授・講師、発達支援センターなどのセンター長などがあげられます。)
―― 発達障害や自閉症を持つ子どもについて研究をされていく中で,自分自身の考え方で変化したことを教えてください。
「人間の発達をどうとらえるか」という考えが一番大きく変わったかなと思います。もともと乳幼児期の子どもの発達に興味をもっていて、最初は「できることが増える」ことが発達であり「子どもをどのように指導、育てていくか」が大事であると捉えていました。研究を進めるなかで多くの子どもたちと出会い「発達の主体は子ども自身であり、大人が発達させるものではない」と思うようになりました。子どもたちと接していく中で、どんなに重い障害があってもその人はその人として生きているわけで、他人が発達させるとか導いてあげるのは非常に傲慢な考え方なんだということに気がつきました。ただ、「発達の主体が子ども自身である」とはいえ、障害があるために発達がスムーズに進みにくいこともありますので、周囲からの支援は必要です。支援では子どもが発達しやすい環境をどう作るのかということが大事だと思います。支援者がしたい支援をするのではなく、子どもにとって必要な支援って何なのかを考えていかなければならないなと考えるようになりました。初めて出会ったときは、障害があるから優しく接しないといけないとか、サポートしなければいけないということを感じていたのですが、それは自分本位な考えだったなと強く感じています。この考え方は障害のある子どもたちに改めて教えてもらったと思います。
また、人間関係って難しいなと思いました。障害のある子どもたちを対象とした研究を行う中で、言葉を使ってコミュニケーションをとることは「当たり前」ではないと気がつくことができました。普段何気なく自分がやっているコミュニケーションがいかに高度なものであるのかを考えずに、それを「当たり前」ととらえてしまうことが怖いなと思います。
―― 人と関わるうえで大切にしていることを教えてください。
究極のところ「他人が考えていることや他人が思っていること」を100%わかることはあり得ないし、逆に自分の気持ちを他者にすべて説明することは難しいものです。なので、いかに自分本位な考え方ではなく、想像して、可能な限り相手の立場に立ちながら、自分のもっている常識をそのまま相手にもあてはめないように気を付けています。相手が何を考えてそのように行動しているのかということをいかに豊かに想像し解釈していくのかということが大事になると思います。特に、子どもと接するときは「相手のことを可能な限り理解しようと努めること」を大切にしています。
―― これから社会に出ていく学生に向けてメッセージをお願いします。
一つは「自分ひとりで抱え込む必要はない」ということです。仕事は一人でするものではないので、何でもかんでもすべて一人でする必要はないと思います。対人援助職を目指す学生にはよく言っているのですが、「専門性が高い」とは「ちゃんと自分自身の守備範囲を理解していること」だと思います。専門家だからといって全てできるわけではないですし、自分自身の専門性でできる守備範囲を理解しておくことが大事だと思います。自分ができる範囲を超えてできないことは誰かに委ねたり一緒にやってもらったりすること、つまりヘルプを上手く出すことが大事だと思います。他者と上手にやっていく上で、相手を信頼してヘルプを上手く出すことも大事なスキルです。他者に助けを求めることはあまりよくないように思うかもしれません。しかし、自分の守備範囲を理解して、守備範囲以外のものは誰かにお願いをしながら少しずつ経験を積んでいき、自分の守備範囲を広げていけばいいと思います。 また、学生の皆さんにはたくさん遊んでほしいです。勉学ももちろん大事ですが、青年期にしか経験できないことがたくさんあります。社会人になってから同じことをしても学生の時とは感じ方や得られるものが異なります。そのため、たくさん遊んでほしいと思います。また、学生時代には「悔いも残してほしい」と個人的には思います。「あの時ああいうこともできたらよかったな」という思いは一見ネガティブな考えのように思えるかもしれないですが、悔いが残っているからこそその時代を振り返るものですし、振り返ってみてその時から変化した自分を感じることや、その当時自分が大切にしていたことを思い出すことにつながるからです。
コロナなどで学生らしい経験がしにくい状況ですが、学生にしかできない経験を積めるよう、濃縮した学生生活を送ってほしいなと思います。