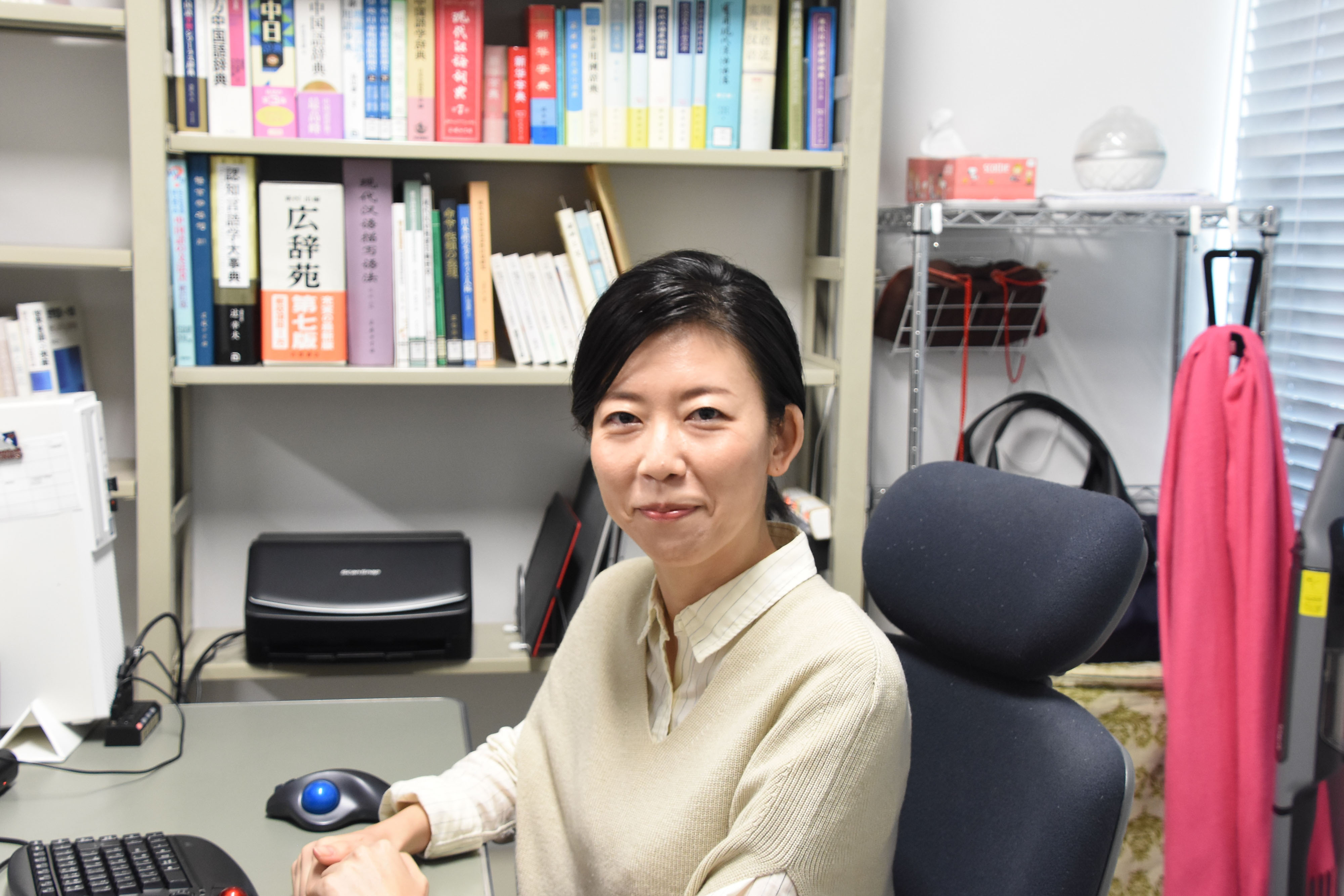現代中国語の程度表現のメカニズム
【ならじょ Today43 号掲載】
前田 真砂美
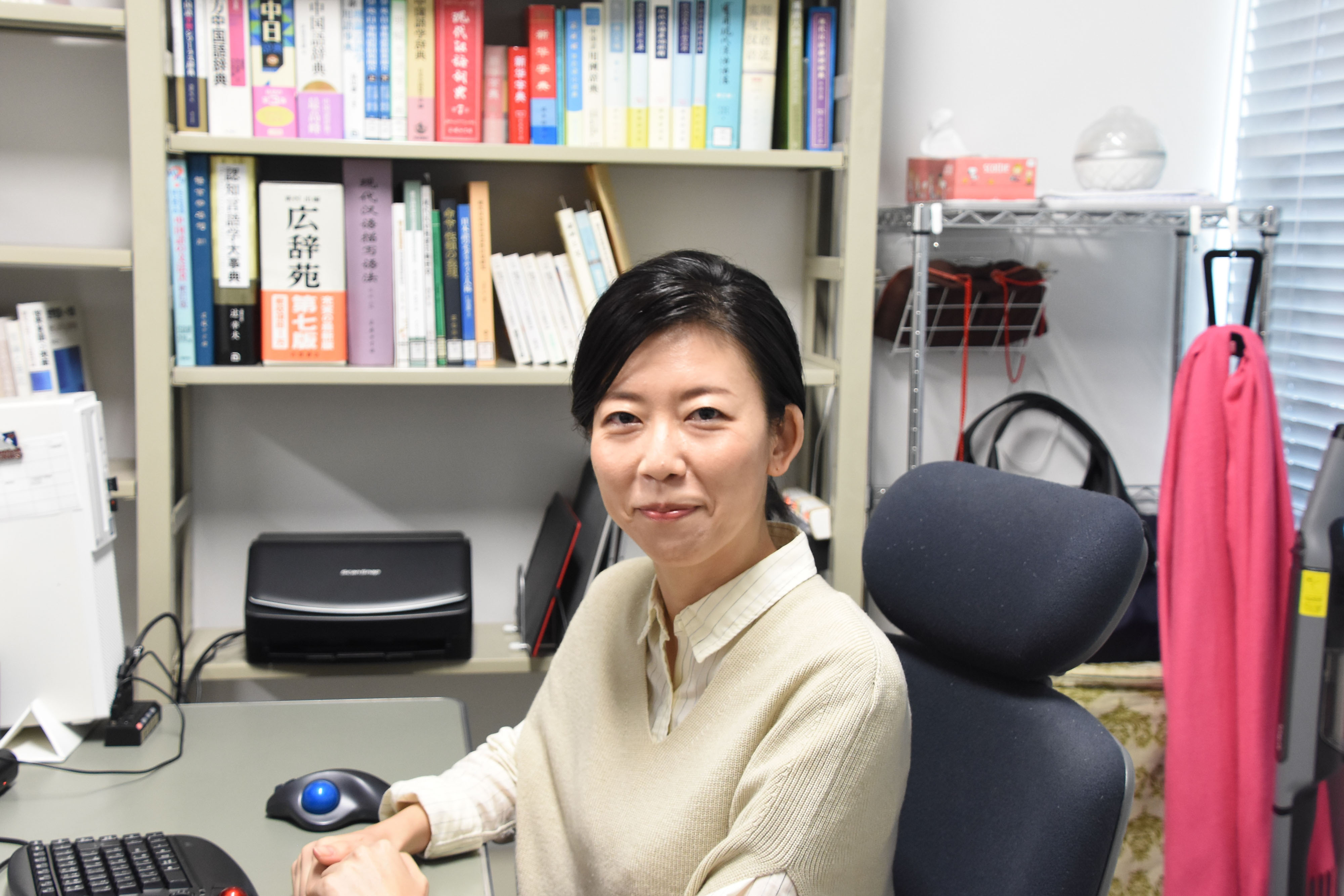
文学部 言語文化学専攻 日本アジア言語文化学コース
【研究テーマ】中国語学
【ならじょ Today43 号掲載】
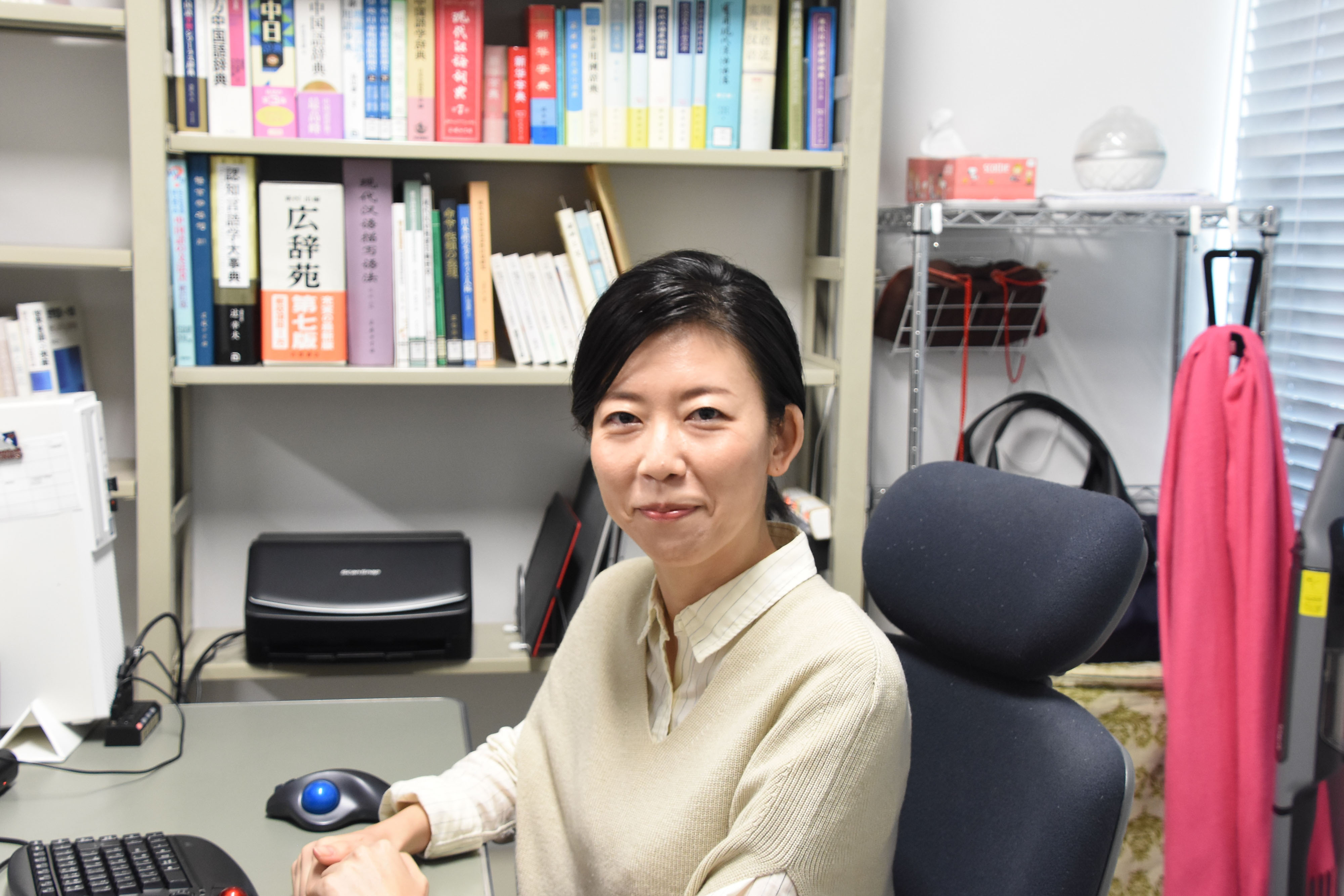
文学部 言語文化学専攻 日本アジア言語文化学コース
【研究テーマ】中国語学
―― 先生の研究内容を分かりやすく教えてください。
中国語の程度表現について研究しています。程度表現というと、日本語では「とても」おいしい、「あまり」寒くない、などがありますが、中国語ではどのような表現を使って高い・低いなどの程度を表すのかを研究しています。また、中国語で程度を表すときに使う「很」や「非常」などの程度副詞はもともと程度を専用に表す言葉ではなく、多くは動詞だったりそれ自体は程度性がなかったりするものでした。そういうものを使って程度を表そうとしているのですが、その裏にはどういうメカニズムがあるのか考えています。もう一つは、中国語ではどのような場面で程度表現が求められるのか、どのようなときに程度を言いたいのかを研究しています。例えば、日本語では、部屋に入ってすぐに「この部屋明るい」と言えますよね。でも中国語では、「この部屋明るい」と程度表現を使わずに言うと、「この部屋は明るい。あっちの部屋は暗い。」とか「この部屋は明るいから本を読むならこっちの部屋に来なさい。」というニュアンスになります。そこが日本語と異なる点です。つまり、程度表現を使うモチベーションが日本語と中国語で異なる可能性があります。どのようなときに程度表現を使いたいのか、それを使うことでどのように話を進めようとしているのか、ということを考えています。
―― 中国語学に興味を持ったきっかけは何ですか。
きっかけは大学三回生のときのゼミです。もともと中国語を専攻語として勉強していたのですが、それまで中国語は私にとって学ぶ対象だったのが、ゼミに入ったことで問題点や疑問を見つけて自分で考える対象に変わりました。なぜこう言うのか、なぜこれは間違いとされるのか、などを自分で仮説を立てて検証していく対象になりました。中国語学に興味を持ったきっかけとしては、中国語を一回生のときから教えてくださっていた先生が文法研究専門の先生で、その方のゼミに入ったので、その出会いが大きいと思います。当時実は、大学四年間びっしり中国語を勉強すれば良いのだと思っていました。そうではなく、中国語を学んでそれを使って自分の専門分野の勉強をしてください、ということでした。三回生になって、歴史や経済、文学などのゼミに分かれてくださいと言われて、中国語がやりたかっただけなのにどうしよう…となり、語学ゼミが一番中国語の勉強になりそう!と思って入りました。結果的にそれが面白かったですね。
―― 研究の楽しい点と大変な点を教えてください
楽しい点は、私が関心をもっている分野の言語研究は機材や現地調査をあまり必要としないので、どこでも何かを考えていられる点です。ふとした一文でも、なぜこう言うのかなと考えたり、街中の中国語の看板を見て、「あっ間違っているな、なんでダメなのかな」と考えたりします。そういったちょっとした素材でずっと考えていられるのが一番楽しいです。大変なことは、その考えていることを文章にしなければいけないことです。特に短い時間で論文を出して成果を出すことが求められるので、十分な時間が取れない中で何とか形にしないと! とひねり出すように書くことがよくあります。
―― 今の目標を教えてください。
近い将来の目標としては、本を一冊書きたいです。大学院生のときから程度表現に関わる研究を続けてきたので、一度それをまとめてみたいと思っています。程度表現はこれからもずっと関心を持ってやっていきたいのですが、他にも興味深いテーマがあり、そちらも取り組みたいです。その前に、一旦これまでの研究をまとめないと次に進めないと思うので、本を書くことが今の目標です。
―― 大学院に進学して、研究を続けようと思った理由は何ですか。
単純に、もっと勉強したいと思ったのが大きいです。というか、それ以外の理由はありません。勉強に熱が入るのも、面白いものを見つけるのも遅かったので、気づいたときには卒業間近という状態で、もう少し学びたいと思い博士前期課程に進みました。そうしたら博士前期課程もまたあっという間で、これでは全然足りない…と思い博士後期課程まで進みました。中国語は一回生のときから勉強してきたのに何も知らないと気づき、もっと深く考えてみたいと思うようになりました。
―― 大学院に行くことの意義や、行ってよかったと感じていることを教えてください。
シンプルですが、勉強が続けられるということです。もちろん日々の生活の中にも学びはあって、大学院ではなくても勉強はできるのですが、大学院で学ぶということは、自分が考えたことや行ったことを他の人と語り合える状態にするという作業が含まれます。発見や気づきを自分だけの言葉で自分だけで理解しているのも良いですが、調査や分析の方法を身につけたり、論証の手順をきちんと踏まえたり、前提を共有したりすると、同じことに興味を持っている人と同じ言葉で語り合えるようになります。そしてそれが次の深い学びに繋がっていきます。これはなかなか得難い経験なので、大学院の魅力はそこにあると思います。
―― 就職のことや女性でドクターまでいくことに不安になったり、周りから何か言われたりしたことはありましたか。
博士前期課程のときに就職も少し考えましたが、幸いなことに両親も大学院に行くことに反対ではなかったので、すんなり進学できました。確かに女性は少なかったですが、周りの先生方が非常に後押ししてくださいましたし、どうにかなるだろうと思って進みました。
―― 奈良女子大学の大学院の魅力を教えてください。
一番の魅力は距離が近いことです。距離が近いというのは、教員と学生の距離が近いというのはもちろん、駅から近くキャンパスがコンパクトであることも重要なことだと思います。本学でずっと学ばれてきた方にとっては当たり前かもしれないですが、教員の研究室と教室が同じフロアにあり、学生さんが行き来しているのは決して当たり前ではありません。大学によっては教室棟と研究棟が離れていて、先生に会いに行くためにはアポイントをとってはるばる移動しなければならないところも少なくないです。それを思うと、何か思いついたときにいきなり教員の部屋をノックできる環境は、とても魅力的だと思います。物理的な近さも結構大事だと思います。本学では歩いていると池の周りや学術情報センター(附属図書館)の前などで色々な人とすれ違いますよね。そういうときに、今日来ているな、とか、あのこと聞いてみようかな、といった自然な交流が生まれるコンパクトなキャンパスは魅力的だと思います。