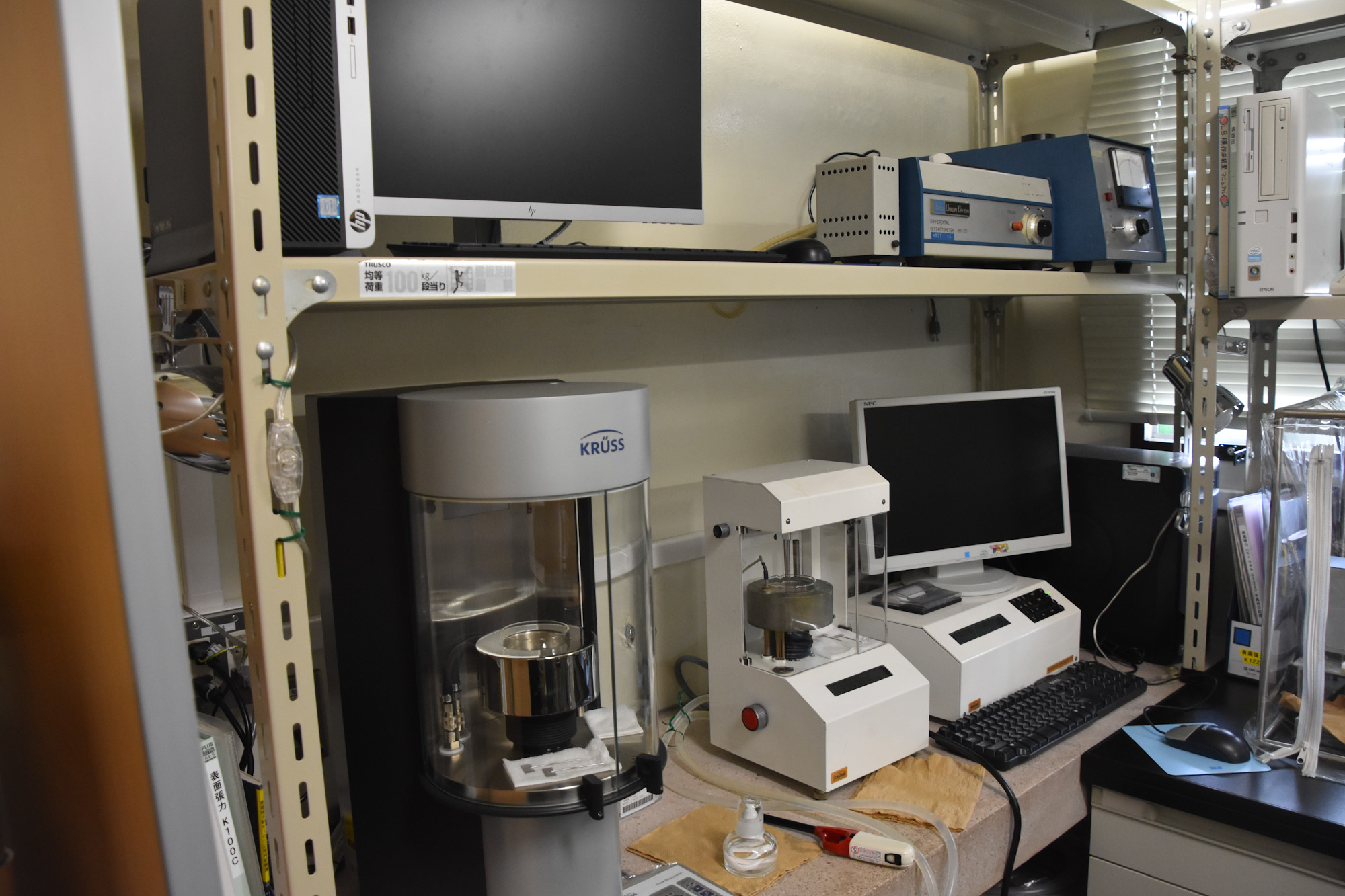コロイド・界面化学の研究
-界面活性剤や高分子、金属ナノ粒子、イオン液体といったソフトマターの構造とその性質-
【ならじょ Today38 号掲載】
吉村 倫一 (よしむら ともかず)

理学部 化学生物環境学専攻 化学コース
【研究テーマ】コロイド・界面化学 / 界面活性剤 / 表面・界面 / X線・中性子小角散乱 / レオロジー / 泡沫 / 乳化