日本では七福神のメンバーとして親しまれている毘沙門天。その姿と役割は長い歴史のなかで驚くほど変化してきました。美術史の方法論を用いて、彫刻作品を中心にその変遷を追っています。
ルーツは古代インド神話の神様です。紀元前5世紀頃に仏教が誕生すると、仏塔を守護する四天王の一人になりました。インドでは王侯貴族の格好で表現されましたが、現在のパキスタンあたりに伝播すると武装した姿に変わりはじめます。かつて中央アジアに存在したホータンでは建国の祖として厚く信仰され、鎧を纏った毘沙門天像の型はここで完成しました。そののち、中国や日本に伝わり、疫病退散や招福の神様としても信仰されています。
毘沙門天研究をはじめたきっかけは、修士一年生のときに参加した中国・敦煌石窟の派遣調査でした。もともとは阿弥陀如来を研究するつもりだったのですが、「阿弥陀仏の研究者はすでに大勢いるなかで、私に貢献できる余地はあるのだろうか」と現地で急に不安になってしまったんです。派遣前に尊敬する先生から毘沙門天をテーマに勧められたことを思い出して、調査の前日に方向転換を決意しました。

敦煌石窟での調査中の一枚
敦煌石窟は、4世紀から14世紀ころにかけて開削された世界三大石窟の一つ。鳴沙山の岩壁に約25kmにわたって400以上の石窟が並びます。石窟内には天井や壁面に描かれた仏画や、たくさんの仏像が収められ、毘沙門天だけでも100体ほどの図像や彫刻が確認されています。すべてをじっくりと観察する時間はないので、2週間ほどでマラソンのように駆け巡りました。そのうち、時代ごとの傾向がなんとなく見えてきて、気づけば毘沙門天に夢中になっていました。
[▶︎関連論文❶「敦煌の毘沙門天王像—石窟内壁画における位置と図像の関連性—」]、[▶︎関連論文❷「中唐・吐蕃期の毘沙門天像に関する一考察」]
いちばん思い入れがあるのは、京都・清凉寺にある毘沙門天像です。平安時代中期に造られた像で、国宝である京都・東寺の毘沙門天像を模刻したものです。
東寺の毘沙門天像は奈良時代に中国・唐から伝来しました。たくさんの模刻が造られましたが、平安時代中期の主流は少しスタイルの違う天台宗系の像でした。では、なぜ清凉寺像は時代を遡って東寺の毘沙門天像を真似たのか。敦煌石窟の調査を終えた私はこの謎に挑みました。
手掛かりは清凉寺のご本尊・釈迦如来立像にあります。エキゾチックな雰囲気のある珍しい姿のお釈迦様で、清凉寺を開いた奝然(ちょうねん)が中国・北宋に渡った際に、インドから中国に伝わったありがたい釈迦瑞像を模刻して日本に持ち帰ったものです。
じつは北宋で釈迦如来の守護神としてセットで祀られることが多かったのが、東寺式の毘沙門天像だったのです。奝然とともに北宋に渡った弟子の盛算(せいさん)はその作法を知っていて、奝然の遺志を継いで清凉寺を建て直した際に、東寺式の毘沙門天像をリバイバルしたのではないかと考えました。
清凉寺像を起点に日本と中国両方の毘沙門天像を考察できたことは、私にとって大きな財産になりました。その後は清凉寺像から中央アジアや東アジアにまで議論を展開し、その成果を『毘沙門天像の成立と展開』にまとめて2022年に刊行しました。長大な時代、広範な地域を対象に、一つのまとまった論を展開できたのではないかと考えています。[▶︎関連論文「京都・清凉寺毘沙門天立像の位置—その造形と製作背景について—」]
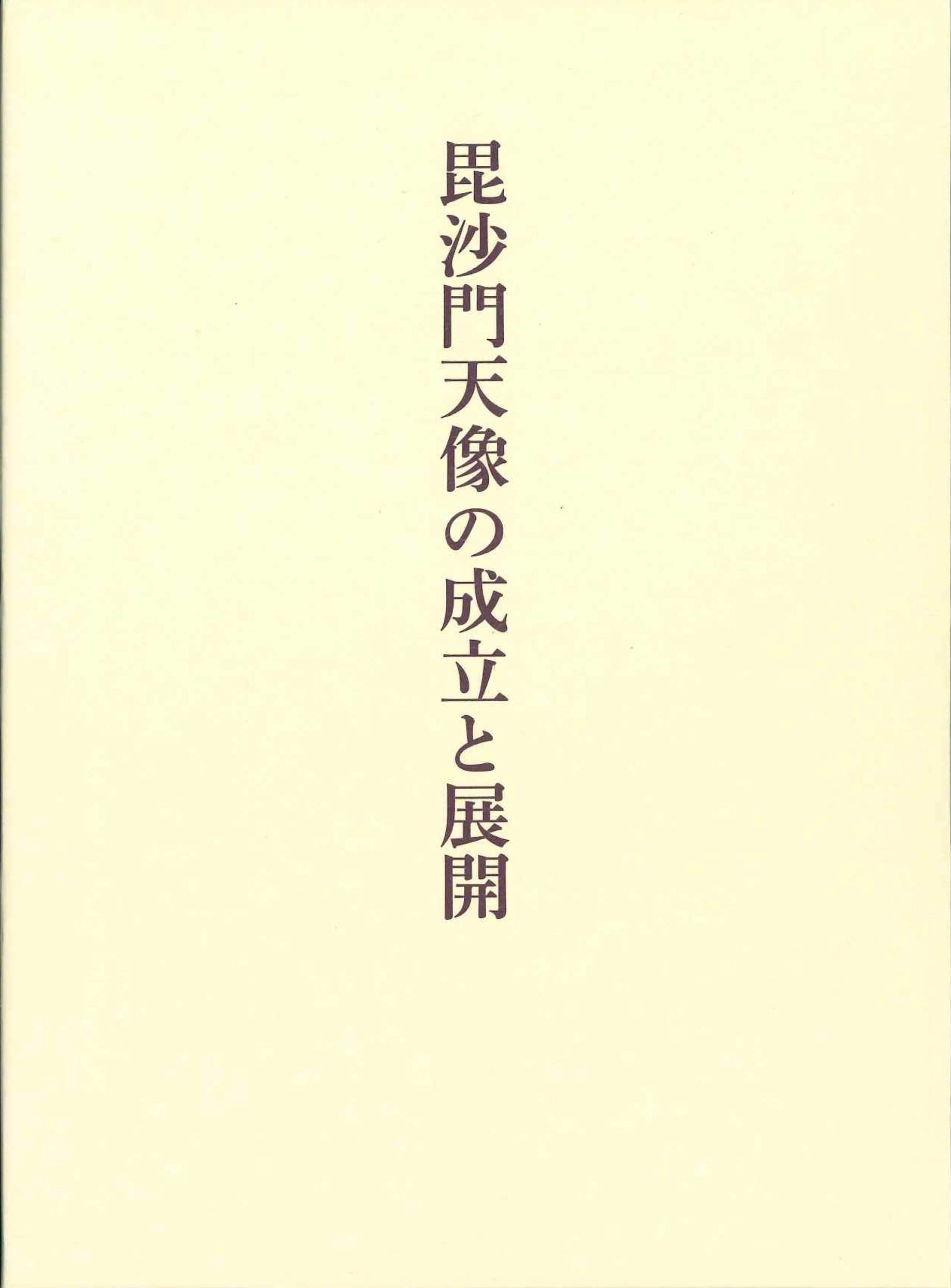
『毘沙門天像の成立と展開』(中央公論美術出版)。
2022年の第34回國華奨励賞受賞を受賞。
最近は法隆寺に伝来する仏教美術の調査にも着手しています。きっかけは聖徳太子。平安時代後期から鎌倉時代にかけて聖徳太子像がたくさんつくられるのですが、なぜか冠に毘沙門天が乗っているんです。聖徳太子が物部守屋と合戦をした際に四天王像を彫って頭に乗せたという伝説がありますが、合戦の絵で、太子の頭上に毘沙門天が描かれているものはありません。なぜ聖徳太子と毘沙門天が結びつくのか。人々が毘沙門天に込めた信仰には、まだまだ謎が隠されています。[▶︎関連論文「聖徳太子と毘沙門天—日宋仏教文化との関わり—」]
毘沙門天像は世界各地に散在していて、今後の調査によっては新たな一面が判明するかもしれません。存在は確認されていても、考察が追いついていない像はアジアだけでも山ほどあります。インドには残念ながらほとんど現存していませんが、ヨーロッパやアメリカにも作品が所蔵されています。海外での調査は大好きなので、新たな毘沙門天との出会いを求めて飛び回ろうと計画中です。
仏教美術には人の心に訴えかける不思議な魅力があります。学生を含め、興味がある人は年々増えていると感じます。仏教美術の魅力に触れ、日本やアジアの歴史と文化の理解が深まれば、きっと心が豊かになるはずです。美術史の研究者として、そのお手伝いができれば嬉しいですね。

東寺像を模してつくられた平安時代の兜跋毘沙門天立像(奈良国立博物館所蔵)(出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム)
絵だと側面や背面の様子はわかりません。立体であることは彫刻の重要な特徴です。東寺の毘沙門天像は多くの模刻を生みましたが、模写と模刻も感覚はまったく違うのだと思います。よくよく観察すると、見た目だけじゃなくて、ボリューム感まで真似ようとしているのがわかります。しかも、真似つつも、模刻当時の流行のスタイルもでてしまっている。とてもおもしろい営みですよね。
美術史だと、図版がいちばんのネックです。仏像の写真を掲載するには寺院や所蔵者の許可が必要ですし、信仰の対象である仏像をインターネット上に公開するのを嫌がる方もいます。大学の紀要では図版だけを白抜きにしてオープンアクセスにすることがありますが、論文の内容を理解するにはやはり紙の論文を取り寄せざるを得ない。難しいところです。