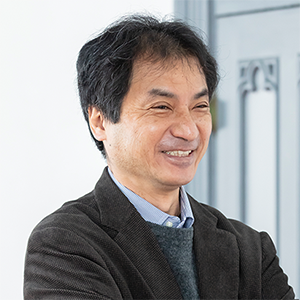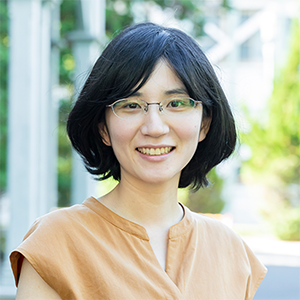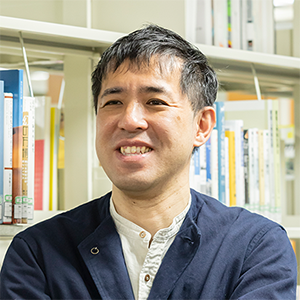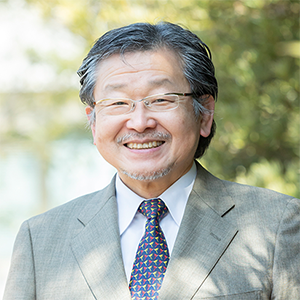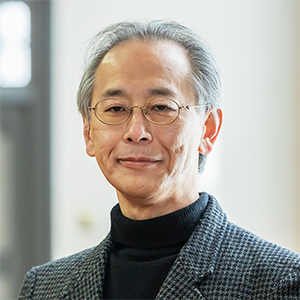人文社会学科
歴史学コース
地理学コース
社会学コース
言語文化学科
日本アジア言語文化学コース
ヨーロッパ・アメリカ言語文化学コース
-
 教授市川 千恵子
教授市川 千恵子専門
- イギリス文学・文化
-
 教授齊藤 美和
教授齊藤 美和専門
- イギリス文学・文化
-
 教授須賀 あゆみ
教授須賀 あゆみ専門
- 英語学
- 言語学
-
 教授マーク・スコット
教授マーク・スコット専門
- Modern American Poetry and Elizabethan Prose
-
 教授高岡 尚子
教授高岡 尚子専門
- フランス文学/ジェンダーと文学
-
 教授竹本 憲昭
教授竹本 憲昭専門
- アメリカ文学
-
 教授イザベル・トノムラ
教授イザベル・トノムラ専門
- フランス文学
-
 教授中川 千帆
教授中川 千帆専門
- アメリカ文学
- ゴシック小説
-
 教授トーマス・ハックナー
教授トーマス・ハックナー専門
- 日本文学
-
 教授吉田 孝夫
教授吉田 孝夫専門
- ドイツ文学
- 民衆文化論
-
 教授吉村 あき子
教授吉村 あき子専門
- 英語学
- 言語学
-
 准教授児玉 麻美
准教授児玉 麻美専門
- ドイツ文学
-
 講師森田 俊吾
講師森田 俊吾専門
- フランス文学
- フランス詩
人間科学科
教育学・人間学コース
心理学コース
子ども教育専修プログラム
-
 教授天ヶ瀬 正博
教授天ヶ瀬 正博専門
- 環境
-
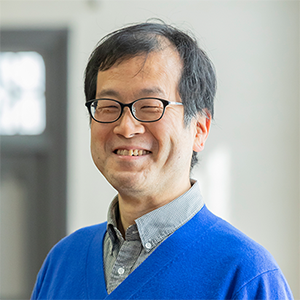 教授鈴木 康史
教授鈴木 康史専門
- 生活
-
 教授中山 満子
教授中山 満子専門
- 人間関係
-
 教授二井 仁美
教授二井 仁美専門
- 教職論
-
 教授藤井 康之
教授藤井 康之専門
- 保育内容指導法(表現・⾳楽分野)、初等教科教育法⾳楽、教育実習、教職実践演習
-
 教授栁澤 有吾
教授栁澤 有吾専門
- 社会
-
 准教授狗巻 修司
准教授狗巻 修司専門
- 特別⽀援論、幼児理解の理論と⽅法
-
 准教授竹橋 洋毅
准教授竹橋 洋毅専門
- 教育実習、教職実践演習
-
 特任教授飯島 貴子
特任教授飯島 貴子専門
- 保育内容指導法(総論)、教育実習、教職実践演習
-
 特任教授功刀 俊雄
特任教授功刀 俊雄専門
- 体育、健康
-
 特任教授伊達 桃子
特任教授伊達 桃子専門
- 英語
-
 特任教授堀本 三和子
特任教授堀本 三和子専門
- 家庭、総合的な学習の時間の理論と実践、初等教科教育法家庭、教育実習、教職実践演習