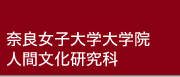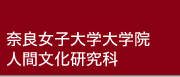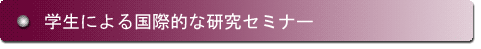
平成19年度
 「学生による国際的な研究セミナー」の開催募集要項
「学生による国際的な研究セミナー」の開催募集要項
<報告>
今回は、東海大学の日本語学科が台湾の窓口となり、日本語と中国語の二ヶ国語でのまちづくりセミナーを実施しました。そのため台中市中心に市民団体、NPO団体、他大学で法律や観光を学び第二外国語として日本語を選択している学生たち約90名が外部から参加してくれました。
「まちづくり」に関しては日本の方が台湾より実践活動、研究が進んでいたという歴史的背景があるため、「日本のまちづくり」の事例発表に対して、台湾の地域を何とか活性化したいと考えられている団体の参加もありました。質疑応答を通して、日本と台湾との共通した問題も見受けられ、今後もネットワークを広げながら課題解決に向けて継続して交流をしていくことの重要性を感じました。
今回のセミナー実施のきっかけは、企画者である柳井が東海大学の日本語学科の林珠雪准教授と出会ったことです。林先生のご主人が、中興大学教授でまちづくりの専門家だったことから、台湾で現在注目されているまちづくりの実践活動団体の代表者に講師としてセミナーに参加してもらうことができました。ちょっとした人との出会い、つながりが大きな力となってくることを実感しました。
また、今回の海外でのセミナー実施について、奈良女子大学諸先生方のご人力があったからこそだと感謝しております。謝金や交通費などの経費を使わせてもらった結果、貴重な体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。


(
文責:社会生活環境学専攻 2回生 柳井妙子 )
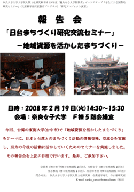
ポスター(.pdf) |
学生による国際的な研究セミナー報告会
日本と台湾のまちづくり
研究交流セミナー
地域資源を活かしたまちづくり
日 時:2008年2月19日(木)14:30〜15:30
会 場:F棟5階会議室 |
<報告>
本セミナーは、内蒙古大学蒙古学学院との学術交流協定が締結されて(2007年12月25日付)、初めての国際交流セミナーとなった。そのため、内蒙古大学副学長で外事も担当しておられる呼格吉勒?教授をはじめ、国際交流掛の担当者にもご出席いただき内蒙古大学及び奈良女子大学両校の交流を進める上でも貴重なセミナーとなった。
また、蒙古学・蒙古文化学・民族学・経済学等の専門家にもご出席いただき、多方面からの議論をもつことができた。
議論の内容としては、モンゴル民族の伝統的な文化である「ゲル」が中国国内でどのように位置づけられ研究されてきたのか、また現在どのような状況にあるのかという話題が中心であった。これは、企画院生の研究テーマでもある。「ゲル」について議論することで、モンゴル民族の伝統的生業形態である「遊牧」や「牧畜」の特徴を理解することの必要性を強く感じた。住居である「ゲル」の実態をとらえることは、モンゴル民族の住環境を含む生活環境全般の変遷経緯の理解に繋がり、またその変遷経緯を知らなければ、「ゲル」を正しく理解できないということを実感した。
更に、住居である「ゲル」のみならず住環境整備にも話が及んだ。その際には、各地域の位置づけや民族別による分類の必要性についても言及され、中国における内モンゴル自治区という特徴のある地域研究の在り方についても現地研究者ならではの意見が出された。
最も印象に残ったのは、院生が奈良女子大学の取り組みについて発表した際、「日本人として、あるいは外国人としてその現象をみたときにどのように感じるか」といった質問が多く出た点である。やはり、現地の研究者が多くの研究実績を積んでいる地域・分野において外国人がどのような視点で課題を見つけ、どのような手法で解決策を見出すのか、その姿勢について大きな関心を寄せられた。この問いに対して明確な回答をできたかと言えば、まだ自信がない部分は多々ある。しかし、私自身の研究を続ける上で常に考え、位置づけなければいけないことであり、このような議論を早い段階で再認識し、現地の研究者と議論できたことは大きな成果であった。
海外をフィールドとして研究する場合、このように現地研究者や更には一般市民との議論を重ねる機会を設けることは、視野が狭くなりがちな調査・研究活動において、丁寧な調査、丁寧な考察の必要性を再確認できる重要な役割をもつと考える。


(
文責:社会生活環境学専攻 2回生 野村理恵 )
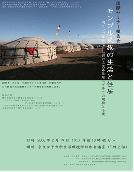
ポスター(.pdf) |
学生による国際的な研究セミナー報告会
モンゴル民族の生活と住居
―内モンゴル自治区における
天幕住居「ゲル」の現状と今後
日 時: 2008年2月19日(木)10:40〜12:00
場 所: 生活環境学部・中会議室 |