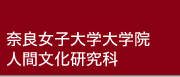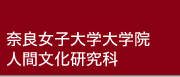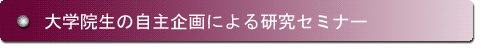
院生自ら企画運営する研究セミナーです。

ポスター(.pdf) |
セミナー(1)
シルクロードのひとびとPART2
ー新疆におけるウイグルの生活と文化の今昔ー」 |
| 日時 |
2007年10月27日(土)13:00〜17:00 |
| 場所 |
本学・大集会室(大学会館2階)
|
| 登壇者 |
〜学外研究者からの話題提供〜
・梅村 坦(中央大学総合政策学部教授・中央アジア史)
「ウイグル農民、職人の生活断章」
・柊谷 龍哉
(株式会社エイチ・アール・エス代表取締役、新疆奥哈邀商貿 有限公司)
「ロプ湖の大魚−新疆の水産業と、その特徴的な魚種−」
〜学内研究者からの話題提供〜
・ライラ ママティ(奈良女子大学・大学院人間文化研究科博士後期課程)
「新疆における女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツ」
・鷲尾 惟子(奈良女子大学・大学院人間文化研究科博士後期課程)
「ウイグルの民間舞踊の多様性と最近の動向」 |
| 趣旨 |
中国新疆ウイグル自治区はシルクロードの要綱として過去に様々な民族が行き交い、社会・文化形態が形成されてきた地域です。大きな社会変化の中にある中国においてこの地域にもその変化の波は訪れています。本セミナーではそうした変化の中にある新疆ウイグル自治区におけるウイグルの生活と文化について、多角的な視点から見ていこうとするものです。) |
| 企画 |
鷲尾惟子ほか(本学大学院生) |
<報告>
昨年度に引き続き、中国・新疆ウイグル自治区に暮らす人々の生活と文化をテーマにセミナーを開催しました。中央大学の梅村先生からはバザールとその周囲に広がる農村との相互的な関係について、鍛冶職人の視点からお話していただきました。
新疆で水産業ビジネスを展開していらっしゃる柊谷氏からは、降水量が少なく四方を山に囲まれた内陸の新疆における水産業の現状について、ご自身の体験とともにお話していただきました。
後半は学内の院生2名の研究発表を行い、留学生のラヒラ・ママティは当地において取り組み始められた女性のリプロダクティブ・ヘルス状況について、また鷲尾からは「歌と踊りのふるさと」と呼びならわされる新疆における民間舞踊の多様性について発表をしました。当地に生きるひとびとの状況について、さまざまな視点から学び、当該地域への理解がより一層深まった貴重な機会を得られたと感じております。
参加者 :講演者2名、本学教員2名、本学院生・学部生10名、学外者18名、計32名
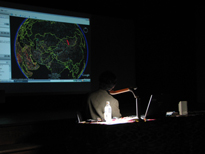

文 責 :博士前期課程 地域環境学専攻2回生 古澤 文
 ポスター(.pdf) ポスター(.pdf) |
セミナー(2)
質的調査の実践的手法
話の聞きだし方、まとめ方
〜プロの記者に学ぶ〜 |
日時 |
2007年10月13日(土)13:00〜15:00 |
| 場所 |
F棟5階会議室 |
| 講師 |
大谷邦郎 氏 |
| 目的 |
人間文化研究科 社会生活環境学専攻
人間行動科学講座 元根朋美 |
| 企画 |
本セミナーは、質的調査の実践的手法を、報道の第一線で活躍されてきたプロの記者に
学ぶことを目的としています。
講師である大谷邦郎(おおたに くにお)さんは、19
61年大阪に生まれ、神戸大学法学部を卒業後、1984年に毎日放送に入社。主に経
済畑の記者として取材を続け、現在MBSラジオ報道部長を務めるものの「MBSラジオ“イ
チ”出たがり記者」として今も様々な現場に出没されています。
また、著書として、就
職課にも置かれている『関西唯(ただ)の人 仕事を楽しむ人図鑑』も出版されていま
す。
卒論、修論等で質的調査を試みている方から、就職活動中の方など、幅広い方に役
立つ講演を予定しています。 |
<報告>
本セミナーは質的調査の実践的手法の習得に焦点化された研修会の開催を目的とし,講師に報道の第一線で活躍され豊富な現場経験をもつ理論家であるMBSラジオ報道部長の大谷邦郎氏をお迎えし「話しの聞き出し方,まとめ方」についてお話いただきました。
最初に参加者に質問や意見を求めながら講義を進めると話されたとおり,22名の参加者が全員参加する形式で取材中に気にかけている手法をお話いただいたあと,質疑応答を行いました。
参加者から質的調査の手法以上の何か色々なもののコツをつかめた,ヒントを頂けた,今後の調査に向けて新たな気づきを発見できたとの感想が多数寄せられたことからも,調査対象者の特性や思考ならびに思想を引き出すための手法習得に大きな示唆が得られました。


文 責 :社会生活環境学専攻 人間行動科学講座 元根朋美

ポスター(.pdf) |
セミナー(3)
質的研究の記述法を探る |
| 日時 |
2007年12月1日(土)14:00〜17:00 |
| 場所 |
生活環境学部中会議室(F棟2階) |
| 講師 |
小宮 友根氏(東京都立大学大学院 博士後期課程)
鶴田 幸恵氏(奈良女子大学大学院人間文化研究科 助教)
中河 伸俊氏(大阪府立大学人間社会学部 教授) |
| 企画 |
人間文化研究科 社会生活環境学専攻
佐藤令奈 |
<報告>
この10年余りにわたり、本邦の社会学ではかつてないほど「質的研究」が持て囃され、多くの研究者によって選択されてきた。そこには従来の社会学が昵近してきた「量的方法」への批判があり、我々はその批判的精神だけに基づいて「質的研究」の選択を是としてきたのではないか。「質的研究」とは何であり、何から何のために何を明らかにし得るのか。実は我々は、その部分に真剣に取り組んだことがないのではないか。
講師のお三方には、それぞれのご研究の理論的・経験的経過から総括して以上のような問題提起に至るまでの道筋をご紹介いただいた。「質的研究」に対する批判的精神を養うと同時に、研究するとは、そのためにはどのように方法を選択していくべきなのか、という、研究の原点に改めて立ち返る機会になった。
多くの方から事前準備の不足をご指摘いただいた通り活発な議論の展開にまではたどり着けなかったが、参加していただいた方々がここでの問題提起を持ち帰り、今後の研究の展開の糧にしていただければ幸いである。


文 責 :社会生活環境学専攻 社会・地域学講座 佐藤令奈

ポスター(.pdf) |
セミナー(4)
社会学的研究における
エスノメソドロジー的無関心 |
| 日時 |
2007年12月12日(水)13:00〜17:30 |
| 場所 |
N339(N棟3階) |
| 講師 |
樫田美雄 (徳島大学) |
| 企画 |
人間文化研究科 社会生活環境学専攻
山本智子 |
<報告>
ー従来の社会学(=常識との落差を「価値」とする社会学)とエスノメソドロジー
のもつ価値観の違いについてー
従来の社会学とは、すでにみんなが知っていること、つまり常識とされているこ
とにおける落差について関心をもってきた。しかし、一方、エスノメソドロジーの関
心は、今まで誰も気づいていないこと(seen but unnoticed=見えているけれども気
づいていないこと)を記述することにある。誰も知らないこと=「場面の秩序」を発
見することがエスノメソドロジーの目的である。
今回のセミナーの題目である「エスノメソドロジー的無関心」の「無関心」とは具体
的にどういうことなのかという問いに対して、「無関心」とは、研究の有用性、改善
可能性、あるいは、戦略的位置づけなど、社会に貢献するという点に関して「無関心
である」とする。たとえば、エスノメソドロジーは、医療現場において、「どのよう
にしたら医療事故が減るのか」といった問いをもたない。こうした現場の改善可能性
を目的にすると、その場の「構造」に巻き込まれ、「〜したら良いのではないか」と
いう価値に巻き込まれてしまい、研究のストーリーがそこに埋め込まれてしまう危険
性がある。よって、エスノメソドロジーは、そうした価値観や目的をもたず、あくま
で「今まで知らなかったこと」を発見することを目的とし、その目的のための「方法
論」としてある。


文 責 :社会生活環境学専攻 山本智子
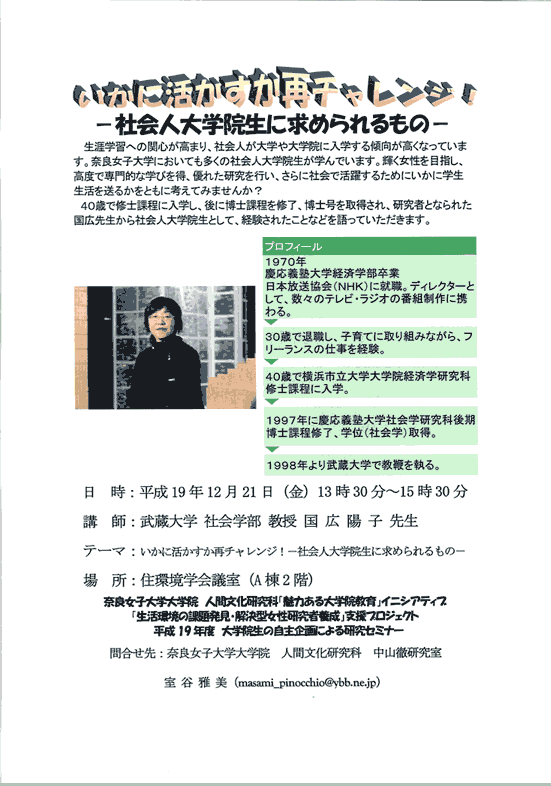
ポスター(.pdf) |
セミナー(5)
いかに活かすか再チャレンジ!
−社会人大学院生に求められるもの−
|
| 日時 |
2007年12月21日(金)13:30〜15:30 |
| 場所 |
生活環境学部会議室(A棟2階 |
| 講師 |
武蔵大学 社会学部 教授 国広陽子 先生 |
| 企画 |
人間文化研究科 社会生活環境学専攻
室谷雅美 |
<報告>
社会人に門戸が開かれ、社会人大学院生が増える一方で、助成金の申請には年齢制限があるなど、研究費を得るのは困難であり、社会人が仕事を持ちながら学業に専念することには、さまざまな問題点もあることから、20年前に社会人大学院生を経験された武蔵大学の国広陽子先生をお招きし、「いかに活かすか再チャレンジ!−社会人大学院生に求められるもの−」と題して、先生が社会人大学院生として学ばれたときの体験や大学に勤務されている日々の経験のなかから感じられたことや問題点・課題などをお話していただきました。
このセミナーを機会に、社会人大学院生のネットワークづくりのきっかけができました。


文 責 :社会生活環境学専攻 室谷雅美