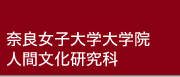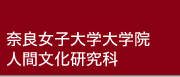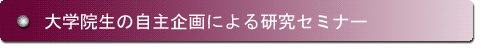
�@
�@
����20�N�x�@�@
�@�@��������^�c���錤���Z�~�i�[�ł��B

�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i1�j
�@�u �V���N���[�h�̂ЂƂт�Part3�v
�@�@�`�|�n��E���E����|�������ւ�
�@�@�@�@
���j�E�����E�����ɑ���u���Y�v�̈Ӌ`�Ƃ́H |
| ���� |
2008�N7��5���i�y�j13:00�` 17:00 |
| �ꏊ |
���w���쓏�r�P�Q�O�����i�n����w�n�}���j |
| ���e |
�@�������k���Ɉʒu����V�d�E�C�O��������͊����n��ɑ����Ă��܂��B���n��̓V���N���[�h�̗v�ՂƂ��Ĉ�ʓI�ɔF�m����A���n�ɋ��Z����ЂƂтƂ͗��j������A�_������A�����ĕ�����K��������A����܂ł̐�����z���グ�Ă��܂����B���̈���ŁA���݂ł͒����̌o�ϔ��W�ƂƂ��ɁA���̒n��ɂ�����Љ�A�����A���͑傫���ω�������܂��B
�@
�{�Z�~�i�[�ł͂��������Љ�Ǝ��R�̕ω��̒��Ő�����ЂƂтƂ̂��炵���e�[�}�Ƃ��āA���p�I�Ȏ��_���痝�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂��B����́A�ЂƂтƂ̂��炵�̒��ł��A�u����i���E����E�n��j�v�Ƃ����l�ԓI�c�݂��L�[���[�h�Ƃ��āA���Y���E�n�����ɏœ_�āA���j�w�E�n���w�E�����l�ފw�E�o�ϊw�Ȃǂ̎��_�����茤���҂Ɏa�V�Șb������Ē����\��ł��B�܂��A���n�̕������f���ŏЉ��R�[�i�[���݂��܂��̂ŁA�ӂ���Ă��Q���������B
|
| ��� |
�Љ�����w��U�@�h���Ҏq�@�ق� |
����
�@�����E�V�d�E�C�O��������ɕ�炷�l�X�̐����ƕ����A���ł�����͂��炵�̒��ɂ���l�X�ȁu����v�Ƃ����l�Ԃ̉c�݂��L�[���[�h�ɂ��ăZ�~�i�[���J�Â��܂����B�܂��A�{�w���m����ے��̌��V���瓖�n�ɂ����čs����_�Ƃ̒n���I�����Ɩȉԍ͔|�ɂ��āA���\���s���A�����ŁA��B��w���m����ے��̓c�掁����͓��n�ɂ����Đ��Y�����ȉԁE�ȕz�̎g�p�Ɛ��Y�̗��j�ɂ��Ă��b���Ē����܂����B
�@
�܂������_�H��w��w�@�A�����m�ے��ɍݐЂ��V�d����̗��w���ł���}�C��������͋ߔN�䓪���Ă����g�}�g���Y�̌���Ɖۑ�ɂ��āA�F�J������̓E�C�O�����̐H���������Ċ����H�����̎�e�Ɖ��ςɂ��Ęb������Ē����܂����B
�@
�����3�x�ڂƂȂ�܂����A����V���Ȏ��_�������A����������w�[�߂Ă����@���ꂽ�Ɗ����Ă���܂��B
�Q���ҁF�u����3���A�{�w����1���A�{�w�@���E�w����8���A�w�O��40���A�v52��
�@
���@�ӁF���m����ے��@�Љ�����w��U�P�� �@���V�@��
�@


�@
 �|�X�^�[(.pdf) �|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i2�j
�@�@�w�J�˂����x�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�[�}�F�u���z�ƂƉJ�ˁv |
���� |
2008�N7��13��(��)�@13�F30�`15�F30 |
| �ꏊ |
�ޗǏ��q��w�@���ۉ��1�K�@���a�� |
| �u�t |
���X�ƐM���@(���z�j�ƁE���z�ƁE������w����) |
| ���e |
�@�J�˂͂���܂łقƂ�nj���邱�Ƃ�����܂���ł����B�J�˂͉ߋ��̂��̂ƌ����邱�Ƃ�����܂��B����������Łu�J�˂̂��鐶���v�����݂��Ă��܂��B����Ȗ����������݂ł���J�˂ɂ��āC�F����ƈꏏ�ɍl�������Ƃ����v������C���̃Z�~�i�[����悵�܂����B
�@
�u�t�ɓ��X�ƐM�������}�����āC���z�j�ƂƂ��Č��z�ƂƂ��Ă݂��u���z�ƂƉJ�ˁv�ɂ��Č���Ă��������܂��B�܂��C���҂ł�����C�Z�����w�̗��ꂩ��J�˂ɂ��Č������Ă���w������̕������Ă��������܂��B |
| ��� |
�Љ�����w��U�@�_�˔����@�ق� |
����
�@��w�@���̎�����ɂ��Z�~�i�[�w�J�˂����x��2008�N7��13��(��)13�F30�`15�F30�A�{�w�������ٍ��ۉ��1�K�a���ɂĊJ�Â����B�u�t�Ɍ��z�j�ƁA���z�ƂƂ��Ċ������̓�����w�������X�ƐM�������������āA�u���z�ƂƉJ�ˁv�Ƃ����e�[�}�ōu�������������B
�@
���X�������z�j�ƂƂ��ďo������J�˂ɂ��āA�܂�����肪�����Z��ɂ�����J�˂ɂ��ē��A�X���C�h��p���Ă��b�����������B���z�G����ʐ^����͂킩��Ȃ��������z�ƂƉJ�˂̊W��J�˂̏ڍׂȂǁA�M�d�Ȃ��b���f�����Ƃ��ł����B
�@
�Q���҂�39���ł���A���̂����{�w�w����12���ł������B
���@�ӁF���m����ے��@�Љ�����w��U3�@�_�˔����@
�@


�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i3�j
�u�ΐl�W��z���ɂ����q�ǂ������ւ�
�����I�A�v���[�`�̓W�J�Ɍ�����
�`�\�����A��e���A��������͂̈琬�`�v
|
���� |
2008�N9��23���i�j14:00�`16:00 |
| �ꏊ |
���w�nN���@N101 |
| �u�t |
�X���@���F��
�i�_�ˑ�w��w�@�l�Ԕ��B���w�����ȁ@�����j
��R�@�䂩�莁
�i���ɐ쏗�q��w�Z����w���c������w�ȁ@�u�t�j |
| ���e |
�@�ΐl�W��z���ɂ����q�ǂ������������Ă��܂��B�Z�~�i�[�̊��҂R�l�́A���̂悤�Ȏq�ǂ������ւ̎��H�I�Ȏ��g�݂��s��������A�u�`�������́i�\�����A��e���A��������́j�̈琬�v�ɒ��ڂ��܂����B
�@ �Տ��S���m�A���y������ɁA�ی��t�̂R�l�̊��҂����ꂼ��̎��H�������A�z�E�̑��l�҂ł�����X�����F���A��R�䂩�莁���炲���������������Ȃ���A�ΐl�W��z���ɂ����q�ǂ������ւ̓����I�A�v���[�`�̓W�J�Ɍ����������I�ȕ�������������Ă��������ƍl���Ă��܂��B |
| ��� |
�Љ�����w��U�@��@�f��@�ق� |
����
�@����̃Z�~�i�[�ł́A�ΐl�W��z���ɂ����q�ǂ������̓`�������́i�\�����A��e���A��������́j���琬����A�v���[�`�ɂ��āA���y������ɁA�Տ��S���m�A�ی��t�̂R�l�̊��҂����ꂼ��̎��H�����ɂ��Ď������A�e����ɑ��Ă���l�̍u�t����A���H�������ɂȂ��Ă������_�ɂ��Ă��w�����������`���Ƃ�܂����B
�@
���H�ł͂Ȃ������_���Ƃ��Ă̘g�g�݁E�V�X�e������������ƍ\�z���A���H�̒��ŋN�����Ă��鎖�ۂ̓W�J�_�𑨂��A�W�J�_���f�[�^�������͂��邱�Ƃ����H�I�����Ƃ������Ƃ����炽�߂ė������邱�Ƃ��ł��A����̌��������ւ̃��`�x�[�V���������߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
���̃Z�~�i�[���A�Q�����Ă������������X�ɂƂ��Ď��H�I�����̂������낳��m�邫�������ƂȂ�K���ł��B
�@
�Q���ҁF�P�S���i�w���W���C�w�O�U���j
���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@�@�l�ԕ��������ȁ@
�Љ�����w��U�@�l�ԍs���Ȋw�u���@�@��@�f��


 �|�X�^�[(.pdf) �|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i4�j
�@�@�uSURVIVE from sexual violence
�@�@�@�@ �\each style & our community�\�v
|
���� |
2008�N10��25���i�y�j
�ʐ^�W�\10�F00�`18�F00�@
�u����\13�F00�`18�F00 |
| �ꏊ |
��w��قQF�@��W� |
| �u�t |
���M���q�i�t�H�g�W���[�i���X�g�j
���S�q
�i��㋳���w�w�Z��@�����^���T�|�[�g�Z���^�[�@�u�t�j |
| ���e |
�@���\�͔�Q�Ƃ����ߍ��ȏ������Ȃ���u����������v�l�X�B�ނ炪����˂Ȃ�Ȃ��̂́A��Q�ɂ�钼�ړI�ȉe�������ł͂Ȃ��̂ł��B�u�����͉̂��Q�҂ł���v�Ƃ���������O�̎������Q�҂����ɋ�����̂́A��̉��Ȃ̂ł��傤�H
�@
�܂��A�ނ�̃X�s�[�N�A�E�g�ɏo��Ƃ��A�u�������v�͂ǂ�������ł��傤�H
�u�ނ�v�Ɓu�������v�̊Ԃɋ��E��������������̂Ƃ́E�E�E�H
�@
���ꂼ��̗���Ő��\�͔�Q�Ɋւ���x���E�[�������Ɍg����Ă����邨������u�t�Ɍ}���A���S���̒��ł����������������ɍl���邱�Ƃ̂ł���@��̒�ڎw���܂��B |
| ��� |
�l�ԍs���Ȋw��U�@�����@���q�@�ق� |
����
�@�{�Z�~�i�[�́A���\�͂����SURVIVE(������������)���e�[�}�ɁA�@���\�͔�Q�҂̎�����L���`���邱�ƇA�Q���ҌX�l�����S���̒��Ő��\�̖͂��Ǝ��g�Ƃ̌q����ɂ��čl������@�����邱�Ƃ̂Q�_��ړI�Ƃ��ĊJ�Â����B
�@
�ړI�@�Ɋւ��āA���\�̓T�o�C�o�[�̑f����B�葱����t�H�g�W���[�i���X�g���M���q���̍u���y�юʐ^�W�u�r�s�`�m�c�v�����{�B
�@
�ړI�A�Ɋւ��ẮA�Տ��S���m�Ŕƍߔ�Q�Ҏx���̎��H�ҋy�ь����҂ł�����S�q���i��㋳���w�w�Z��@�����^���T�|�[�g�Z���^�[�u�t�j�̍u���uThey/We�\�w�����ҁx�Ɓw���x�̊Ԃɂ�����́\�v�����{�����B
�@
�܂��A�ړI�A�̌��ʂ̋��L���Ӑ}���ču����ɐ݂����P���Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����^�C���ł́A���\�̖͂��ɂ��ėl�X�ȗ���i��Q�o���ҁE��Q�҉Ƒ��E����E�i�@���j�ŊS���������̕����瑽���̔��������A���𗬐��̍����Z�~�i�[�ƂȂ����B
�@�u�t�������Q���҂�25���A�����{�w�w���y�ы�����8���ł������B
���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@�@�l�ԕ��������ȁ@�l�ԍs���Ȋw��U�@�����@���q


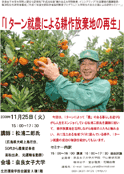
�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i5�j
�uI�^�[���A�_�ɂ��k������n�̍Đ��v
|
���� |
2008�N11��25��(��)�@15�F00�`17�F30
15�F00�`16�F00�@�u����@�@
16�F00�`17�F30�@���𗬉� |
| �ꏊ |
�������w����c���@A��1�K |
| �u�t |
���Y��Y��
�i�L�������㓇�ݏZ�A50�Αォ��_�Ə]���ҁA
�@
�����o�g�A���^�A�ȋΖ��j |
| ���e |
�@���R�Ԓn��ɂ����ẮA���ݏW���̏��K�́A������i��ł��܂��B�����ł́A����܂ł̍s���哱����A���Ԃ̑��l�Ȏ�̂��n��Â���̒S����Ƃ��Ċ������邱�Ƃ����߂��Ă��܂��BI�^�[���ł̈ڏZ�҂����̒S����̈�l�Ƃ��čl�����܂��B
�@
�s�s�s�������R�Ԓn��ɓ��荞�݁A�n��̐l�ɔF�߂��n��Â���̒S����̈�l�ɂȂ�܂ł̉ߒ���m�邱�Ƃɂ���āA�����\�Ȓ��R�Ԓn��ւ̃q���g�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂��B
�@
����́AI�^�[���ɂ���āu�_�v�̂����炵�𑗂�Ȃ���l�����G���W���C���Ă��鏼�Y��Y�����u�t�ɏ����āA�k������n�����p���Ȃ���n��̐l�����ƐG�ꍇ���A���Ɋ��͂���n��Â���ɗ��ł���l�q�AI�^�[���A�_�̐����̔錍���Љ�Ă��炢�܂��B |
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�@���R�O�������@
���䖭�q�E���J����E�ԗ֗R�� |
����
�@ �{�Z�~�i�[��2008�N11��25���i�j15�F00�`17�F30�A�������w����c���ɂ����āA�Ԃ̗�����Y����_���o�c�҂̏��Y��Y�����u�t�Ɍ}���J�Â��܂����B���Y���͉^�A�Ȏ���ɊC�O100�s�s�����D���Ƃ��ċΖ�������A�����ň��H�ƌo�c�A�o�ŋƋΖ���A55�ōL�������㓇�ɈڏZ���Ĕ_�Ƃɏ]������I�^�[���A�_�҂ł��B���݂́A���_���JAS�K�i���擾�����u���[�x���[�͔|�A�݂���͔|�A�V�V���A�̃g�}�g�͔|�A�����ăo�����o�c������Ă��܂��B
�@
����A���Y�����I�^�[���A�_�ɂ�鐬���̔錍��I�^�[���ɊS�̂���l�ւ̒��܂����B�����̔錍�́A�@���n�������Ă����l�Ƃ̏o��i�y�n�m�ہc�n���I�s�j�I�����[�_�[�A�͔|�c�t���̊m�ہ@�A�k������n���Đ����p���邽�߂̉ۑ�i�y�n�Əo�����A�y�n��m��c�n���̐l�̏����A�I���W�i���ȍH�v�c�I�[�i�[���x�Ȃǂ̃`�������W�j�@�B�f�l���o�̔_�Ɓi���X�̎G���c���_����A�C�y�ɉ��ł��V�K�͔|�j�����{���Ă��邻���ł��B
�@
���ꂩ��A�_���悤�ƍl���Ă���l�ɑ��ẮA�@���m�ȖړI�ݒ�i���ꂩ�牽���������̂��H�j�A�Ⴂ�N��ł̈ڏZ�i��N����ł͒x������̂��H�j�B�����̐��E�͎����őn��@�C�l�����O�������Ďd���Ǝ���y���ށ@�D�Љ�v���Ȃǂ̘b�����܂����B
�@
�l���������i��ł��钆�R�Ԓn��ɂ�����I�^�[���AU�^�[���AJ�^�[���̐l�����̑��l�Ȏ��_�A�m�b�A�Z�p�A�l�b�g���[�L���O�́A����n��̊��͌��ɂȂ��Ă������̂Ǝv���܂��B���H����������Ă��鏼�Y���̘b���́A�n��Đ��ɂ����đ�ϋM�d�Ȃ��̂ł����B
�@
�p�l���X�g�ȊO�̎Q���҂�13���ł���A���̂����{�w�w���E�@����8���A�s��3���A�s��1���A����w����1���ł����B
�@���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@�@�l�ԕ��������ȁ@�Љ�����w��U�@���䖭�q



�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i6�j
���E��Y v.s. ������܂��̕��i�@
��P��@�w�p�̊፷���x
|
���� |
2008�N11��28��(��)
17�F00�`�i��t 16:00�`�j |
| �ꏊ |
���؉�@�Ȃ�܂��i�ޗǏ��q��w�@�ޗǒ��Z�~�i�[�n�E�X�j
�Z���F�ޗǎs�����咬
�i���؉�HP)
http://www.narawu.ac.jp/gp/naragp_ex/seminar_house.html |
| �u�t |
�X�{�@�������@
�i���厛���y�@�@�Z�E�j
����@���Ǝ��@
�i�ޗǏ��q��w�@�������w���@�Z���w�ȁ@�����j |
| ���e |
�@���j�s�s�ޗǁB�����ł͐��E��Y�Ɠ��퐶�����ׂ荇���A�܂��A�����ɐ��E��Y�����邱�Ƃ�������܂��̕��i�ƂȂ��Ă�������܂�Ă��܂��B���j�╶�����A�ȂƑ����Ƃ������Ƃ̖{���́A�V���̂��̂��݂������ߍ����Ȃ���A���̓y�n�ɍ��t���Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�{�Z�~�i�[�́A�A�����Ƃ��Č��z�E�s�s�v��̃v���t�F�b�V���i�����Q�X�g�Ɍ}���A�Q�X�g���m�̑Βk�ƃQ�X�g�ƒ��O�̑Θb�̓\���ŗ��j�s�s�ޗǂ̍���̂��肩���ɂ��ĒT�����Ă������̂ł��B
�@
����ڂ́A�Q�X�g�Ƃ��āA���z�j�E������Y�̕ۑ��Ɗ��p����Ƃ���Ă���{�w�@���䐳�Ƌ����Ɠ��厛�����@�Z�E�@�X�{�����������}�����A���ꂼ��̗��ꂩ��A�w�p����镶���x�ɂ��Č���Ă��������܂��B |
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�@�Z���w��U
�؎u�ہE��c��G�E���V�����E���c�^�|�E���c�b�� |
| �₢���킹�� |
m_pro_narajyo@excite.co.jp |
����
�@
�@�{�Z�~�i�[�́A���ʂ̃e�\�}�u���E��Yv.s.������܂��̕��i�v�Ƒ肵�A�e���ʂ̌��z�E�s�s�v��̃v���t�F�b�V���i���ɂ��ꂼ��̐��̈�̗��ꂩ��A���j�s�s�ޗǂ̍���̂�����ɂ��ċc�_���Ă��������A�A���Z�~�i�[���̑�P��ł������B�Q�X�g�Ƃ��ē��厛�����@�̏Z�E�ł�����X�{�����������������A�{�w�������w���̑��䐳�Ƌ����Ɓu�p�̊፷���v�Ƒ肵�āu�p����镶���v�ɂ��đΒk���Ă��������܂����B
�@
��1����Βk�`���A��2���O�������Ă̍��k��`���ō\�����A���̌�A��2���̑����Ƃ��āA���H�������Ȃ��炨�b�̉���s���܂����B�Ў����z�Ȃǂ̃n�[�h����s����ՂƂ������\�t�g�܂ŁA������v�f�ɂ���Ďp����Ă����A���݂ł͂�����܂��Ƃ���Ă��镗�i�ɂ́A1300�N�ԓr��邱�ƂȂ������Ă����s�s�E�ޗǂ̐������B��Ă���Ƃ������b���f���܂����B�����̒S����Ƃ��āA�������������̈�[��S���Ă���Ƃ�������ƁA1300�N�Ƃ������̏d���Ɏv�킸���Ґk�������Ă��܂��قǂł����B�܂��A���b�̉�ł͐X�{���𒆐S�ɁA�Z�E�Ƃ����E�Ƃ�C���ɂ��ċM�d�Ȃ��b���f�����Ƃ��ł��܂����B
�@�u�t�������Q����16���A�����{�w�w���y�ы���10���ł����B
�@���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@�@�l�ԕ��������ȁ@�Z���w��U�@���@����


�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i7�j
�@�@�@�@�@
��s�o�Z�ւ̎Љ�\�z��`�I�ڋߣ |
���� |
2008�N12��6���i�y�j�@
13�F30�`17�F30
|
| �ꏊ |
�����������@���w�n�m���@�R�R�X���K��
|
| �u�t |
�H���G�i��
�i���{����w�l�ԎЉ�w���@�u�t�j |
| ���e |
�@�@�s�o�Z�ɑ��錩����l���������l������Ȃ��ŁA����x���Z���^�[�i�K���w�������j�̐�����t���[�X�N�[���ւ̏o�Ȃ��o�Z�����ɃJ�E���g�����Ȃǂ��܂��܂ȑΉ��������Ȃ��Ă��܂��B�������A�����҂ł���q�ǂ��E�e�E���t�Ȃǂ��̑����̐l�X�́A�s�o�Z�ł��邱�ƂňˑR�Ƃ��Đ����Â炳���������Ă��܂��B
�@�{�Z�~�i�[�ł́A�u�t�ɍH���G�i�������}�����A�ߔN�A���ڂ���Ă���u�Љ�\�z��`�v�̍l�������肪����Ɂu�s�o�Z�v�Ƃ�����̌��ۂ��u�Љ���v�Ƃ��čl���邱�Ƃʼn��������Ă��邩�A���b�����f�����܂��B��Љ�\�z��`��Ƃ͉����A��ʂ��ĕs�o�Z�𗝉�����V���Ȏ��_��T���Ă��������Ǝv���܂��B
|
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�@�Љ�����w��U�@
�y���R�N�q�E�N��T�q |
����
�@�{�����Z�~�i�[�́C�u�s�o�Z�ւ̎Љ�\�z��`�I�ڋ߁v�Ƒ肵2008�N12��6���i�y�j13:30�`17:30�A�������������w�n�m��339���K���ɂ����āA���{����w�̍H���G�i�����u�t�ɂ��}�����J�Â��܂����B
�@
�u�s�o�Z�v���͂��߁A���݂́u�Ђ�������v��u�j�[�g�v���̎Љ�w�I�����ł�������̍H�����ɁA�ߔN�A�Љ��茤���ɂ����ďd�v�ȗ��_�I�����̈�ł���u�Љ�\�z��`�v�ɂ��āA���؎�`�����Ƃ̔�r��ʂ��Ă��̓�������b�I�Ȃ��Ƃ���ڂ������u�`���Ă��������܂����B�܂������ɁA�Љ�w�ɂ�����s�o�Z�����ɂ��ċM�d�Ȏ�������Ă��������A�t�B�[���h�����ɂ��Ă����b�����������܂����B�Љ�\�z��`�Ƃ͉�����ʂ��č����A�Љ���Ƃ����Ă���u�s�o�Z�v���ۂɑ���V���Ȏ��_��@��ƂȂ�܂����B
�@
�Q����12���A�{�w�w��9���B
�@���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@ �l�ԕ��������ȁ@�Љ�����w��U�@ �y�� �R�N�q



�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i8�j
���E��Y v.s. ������܂��̕��i�@
��2��w�s�̌`���x
|
���� |
2008�N12��12���i���j
17:00�`�i ��t 16:00�` �j |
| �ꏊ |
���؉�@�Ȃ�܂��i�ޗǏ��q��w�@�ޗǒ��Z�~�i�[�n�E�X�j
�Z���F�ޗǎs�����咬
�i���؉�HP)
http://www.narawu.ac.jp/gp/naragp_ex/seminar_house.html |
| �u�t |
��t�w��
�i���z�Ɓ@������w��w�@�@�H�w�n�����ȁ@���z�w��U�@�y�����j
���c���V��
�i���z�Ɓ@�ޗǏ��q��w�@�������w���@�Z���w�ȁ@�y�����j |
| ���e |
�@���j�s�s�ޗǁB�����ł͐��E��Y�Ɠ��퐶�����ׂ荇���A�܂��A�����ɐ��E��Y�����邱�Ƃ�������܂��̕��i�ƂȂ��Ă�������܂�Ă��܂��B���j�╶�����A�ȂƑ����Ƃ������Ƃ̖{���́A�V���̂��̂��݂������ߍ����Ȃ���A���̓y�n�ɍ��t���Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�{�Z�~�i�[�́A�A�����Ƃ��Č��z�E�s�s�v��̃v���t�F�b�V���i�����Q�X�g�Ɍ}���A�Q�X�g���m�̑Βk�ƃQ�X�g�ƒ��O�̑Θb�̓\���ŗ��j�s�s�ޗǂ̍���̂��肩���ɂ��ĒT�����Ă������̂ł��B
|
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�@�Z���w��U
�؎u�ہE��c��G�E���V�����E���c�^�|�E���c�b�� |
| �₢���킹�� |
m_pro_narajyo@excite.co.jp |
����
�@�{�Z�~�i�[��2008�N12��12���i���j17�F00�`�A�Ȃ�܂��ɂ��鐳�؉Ɓi�ޗǏ��q��w�@�ޗǒ��Z�~�i�[�n�E�X�j�ɂ����ĊJ�Â��܂����B���ʂ̃e�\�}�u���E��Yv.s.������܂��̕��i�v�̂��ƁA�e���ʂ̌��z�E�s�s�v��̃v���t�F�b�V���i���ɂ��ꂼ��̐��̈�̗��ꂩ��A���j�s�s�ޗǂ̍���̂�����ɂ��ċc�_���Ă��������A�A���Z�~�i�[���̑�Q��Ƃ��čs���܂����B
�@
����̃e�[�}�́u�s�̌`���v�Ƒ肵�܂��āA���������_�Ɍ��z�ƂƂ��Ă�����Ă����t�w ������w��w�@�y�������Q�X�g�ɂ��������A�{�N�x���{�w�ɒ��C�̒��c���V�y�����ƂƂ��ɁA���E��Y�Ƃ�����܂��̕��i�Ƃ����ЂƂÂ��̊��̒��ɂǂ̂悤�ȃ��[�������藧����T�����Ă��������܂����B�Z�~�i�[�͑�1���̐�t�搶�̍�i���N�`���[�A��2���̒��O�������Ă̍��k��ō\������Ă���A��2���͉�ꂪ��̂ƂȂ����c�_�ɑ傢�ɐ���オ��܂����B
�@
�Â��ǂ����̂������c�邱�̓ޗǂŁA�����P�ɌÂ����̂Ɏ����ĐV�������̂����Ƃ������Ƃ������A�ޗǂ炵�����c�����@�Ȃ̂ł��傤���B��t�搶�����z�����ۂɍl���邱�ƁA����͂��̏ꏊ�̓�����ǂݎ��A���̗v�f�����݂Ƃ��ĐV�������̂ɔ��f�����č��Ƃ������Ƃł����B���̌��z�������Ƃɂ���āA�����̏ꏊ�炵�������Ԃ肾�����悤�Ȏ�@�B���̃v���Z�X���ȂČ�����܂��Ƃ������̂��l���邱�ƂŁA�ޗǂ炵�����c�����V���ȓޗǂ̕��i�����܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂�
�@
���z�����v���Z�X���͂��߁A���z�ƂƂ��̏ꏊ�A�܂������ɏZ�ސl�Ƃ̊W�ȂǁA�M�d�Ȃ��b���f�����Ƃ��ł��܂����B
�@
�u�t�������Q����72���A�����{�w�w���y�ы���53���ł����B
�@���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@ �l�ԕ��������ȁ@�Z���w��U�@���c�b��


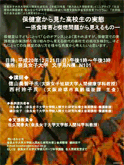
�|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@�Z�~�i�[�i9�j
�@�@�@�@�@
�ی������猩�����Z���̎���
�[�ېH��Q�Ƌi����肩�猩������́[ |
���� |
2008�N12��21��(���j
13�F00�`15�F00
|
| �ꏊ |
�ޗǏ��q��w�@���w�nN���@N101
|
| �u�t |
���R���q�q��
�i��㏗�q�Z����w�@�l�Ԍ��N�w�ȁ@�����j
������q���@
�i���{��s������ہ@�卸�j |
| ���e |
�@�Љ�̕ω��Ƌ��ɁA�������k�̌��N���i��{�싳�@�����ʂ�����͕ω����Ă���B����ł́A�ېH��Q�A�����߁A�s�o�Z�A���p�ȂǗl�X�Ȗ�肪�������Ă���A�ی����͐S�ɔY�݂����q�ǂ������́u�S�̋��ꏊ�v�ƂȂ��Ă���B
�@
�{�싳�@����̓I�Ɋw�Z����łǂ̂悤�Ɏq�ǂ��B�Ɗւ���Ă���̂��A�ېH��Q�̂��鐶�k�̎���ƁA�莞�����Z�ł̋։��x���̎���𒆐S�Ƃ��āA�ی����Ƃ������ʂ��Č���̍��Z���̌������܂��B
�@
�����A�{�싳�@�̐E����A�w���X�J�E���Z�����O������������Ă��铿�R���q�q�搶����A����̍��Z������芪�����_���Ă��������A�Q���ґS�̂Ō����������Ǝv���܂��B
|
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@ �l�ԕ��������� ���m����ے�
��c�G�q�@�ق� �@ |
����
�@
�@ �ی����͎q�ǂ��ɂƂ��āu�S�̃I�A�V�X�v�ƌ����ċv�������A���\��2���͌��E�̗{�싳�@�Ƃ��č��Z�ɋΖ����Ă��邪�A�w�Z����œ��X���g��ł�����H�ƌ����̒�����A�@���Z���̐H�s���Ɋւ�����ԕA�A�莞���ɂ�����։�����̂Q������ꂼ�ꌤ�����\�����B
�@�������\�̍u�]�́A��㏗�q�Z����w�̗{�싳�@�{���ے��ŋ��ڂ��Ƃ��Ă���A���R���q�q����肢���������B���R���͗{�싳�@�̐E�������A�w�Z���N���k�����ɂ��ē��ɑ��w���[�����A�u�]��́u�Q�P���I�̗{�싳�@�Ɗw�Z�ی����S�@�v�Ƒ肵�ču�������Ă����������B���݂̊w�Z�ی��@�������Q�P�N�S���Ɋw�Z�ی����S�@�ɉ�������邪�A�u�{�싳�@�Ƃ��ċ��߂��鎑���Ɣ\�́v��Ƃ��A�{�싳�@�ɑ��ĔM���G�[���𑗂�����e�ł������B
�@���ӁF�ޗǏ��q��w��w�@ �l�ԕ��������� ���m����ے��@
��c�G�q

 �|�X�^�[(.pdf) �|�X�^�[(.pdf) |
�@
�@���m����ے��E�����}�l�W�����g�Q���ƉȖځ@
�@�@�u�����v���W�F�N�g���K�v��u���ɂ����
�@�����J�Z�~�i�[��
�@�@�w�u�����Ёv�̌���Ɖۑ�
�@�@�@�@
�\�\�Ƒ��A�A�C�f���e�B�e�B�𒆐S���x
|
���� |
2008�N11��11��(��)�@
14�F40�`17�F00
|
| �ꏊ |
�ޗǏ��q��w�@�e���T�K�@�l�ԕ��������ȉ�c���@
�Q�������A�\�����ݕs�v |
| �u�t |
�� �V�� ���i���������w�����ُy�����j |
| ���e |
�@���܂ꂽ�ꏊ�����̐l�̂ӂ邳�Ƃł���A�܂��A���܂ꂽ���̍��Ђ������ƂR�ł���ƍl���Ă���l���قƂ�ǂ�������܂���B�������A���������m��Ȃ��u�����Ёv�Ƃ�������A�܂�A���Ђ̂Ȃ��l�тƂ��������݂��Ă��܂��B
�@
�{�Z�~�i�[�ł́A���{�E���l�̒��؊X�ɐ��܂�炿�A�����g���u�����Ёv�������o�������� �� �V�� �� �ɁA�����������Ƃ����Ă݂߂Ă���ꂽ�A���{���͂��߂Ƃ������E�́u�����Ёv�̐l�тƂɂ��āA�u�Ƒ��v�u�A�C�f���e�B�e�B�v�Ƃ����L�[���[�h�ł��b���������܂��B
|
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�l�ԕ��������ȎЉ�����w��U
�u�����v���W�F�N�g���K�v��u�� |
| �₢���킹�� |
nara.wu.pj@gmail.com |
|
�@
2008�N�x
�u�����v���W�F�N�g���K�v��u���ɂ��
���Z�~�i�[�̎����
|
���� |
2008�N12��11��(��)�@10�F40�`
|
| �ꏊ |
�ޗǏ��q��w�@�e���T�K�@�l�ԕ��������ȉ�c�� |
| ���e |
�@�{��ł́A�u�����v���W�F�N�g���K�i�����}�l�W�����g�Q�j�v��u������悵���Q�̃Z�~�i�[�w�ΐl�W��z���ɂ����q�ǂ������ւ̓����I�A�v���[�`�̓W�J�Ɍ����ā`�\�����A��e���A��������͂̈琬�`�x�i�X��23���J�Áj�A�w�u�����Ёv�̌���Ɖۑ�\�Ƒ��A�A�C�f���e�B�e�B�𒆐S�Ɂx�i11��11���J�Áj�̊��E�^�c�Ɋւ��āA���ꂼ��̃O���[�v�����\�������܂��B
�@
���\�ł́A�Z�~�i�[�̊��ⓖ���̃Z�~�i�[�^�c�܂��A����܂ł̐��ʂ�U��Ԃ�A����̑�w�@���̂��߂̋���J���L�������̒��ŁA�������u�����v���W�F�N�g���K�v��u��������ꂽ���ʂ�������܂��B����A��w�@���ɂ�鎩����Z�~�i�[���v�悳��Ă���@���̕��X�ɂƂ��Ă��A�Z�~�i�[�J�Âɂ������Ă̗����H�v�A���ȓ_�ȂǎQ�l�ɂ��Ă��������邩�Ǝv���܂��̂ŁA�F���܂��U�����킹�̂������Q�����������B
|
| ��� |
�ޗǏ��q��w��w�@�l�ԕ��������ȎЉ�����w��U
�u�����v���W�F�N�g���K�v��u��
�^����b���q�E��~�E�Q�����`���N�E�e�r�c�q |