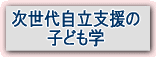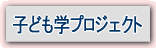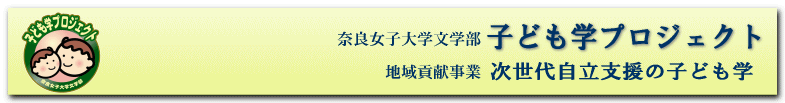 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
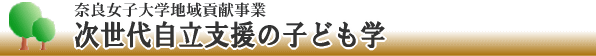 ■平成20年度の企画 平成20年度に実施した企画で、すべて終了しています。 子ども学は「子どもの生きる現場」からはじまります。 その子どもたちの生きる現場である、家庭・地域・学校が、いずれもいま大きく変容しつつ あります。 「子ども学プロジェクト」では、この時代の変化に対応して、関連諸科学との連携のもと、子どもの現実に食い込むことのできる実践的な子ども学の構築を目指してきました。 プロジェクト発足以来6年目を迎えますが、この間、地域貢献事業での実践・研究は その中核的な役割を担ってきました。 平成20年度もまた、これまでの成果を踏まえて、以下の4つのプロジェクトを連動させ、 あらたな展開を求めました。 【企画1】特別支援教育と子どもたちのいま――発達と障害と子どもたちの暮らし はじまったばかりの「特別支援教育」を議論の俎上に乗せて、子どもたちがいま、学校で、地域で、どのように生きているのか、その「生きるかたち」を問います。 【企画2】若草中学校区連携プロジェクト 中学校区全体の教育機関の連携によって進められる子どもの発達支援を応援します。 【企画3】子どもの生活臨床 児童養護施設等から心理的援助のニーズや問題点、創意工夫を調査し、それに 対する効果的な対処と改善策を大学院附属心理教育相談室との協力や施設職員向 け研修会の開催によって図ります。 【企画4】若手教員応援プロジェクト 子どもの自立支援の担い手である教師の成長過程を展望し、問題解決の手がかりや 足がかりを共に考えていくキャリア形成支援を行います。
 特別支援教育と子どもたちのいま 特別支援教育と子どもたちのいま――発達と障害と子どもたちの暮らし (公開連続講演会・一般) 人間も自然の一つ、その子どもたちの個性、能力は、個々にさまざまです。そこで子どもたちへの教育は、その個々の個性、能力に応じたものでなければなりません。それは当然のことです。昨年度にはじまった特別支援教育は、少なくともその建前では、こうした理念のうえに立てられたものでした。しかしこの理念を現実のものとするのは容易なことではありません。じっさい、「個々に応じた教育」を標榜することが、結果として、子どもどうしを個々に分断する結果になる危険性はないのでしょうか。また、そのことによって子どもたちの人間関係の網の目(ネットワーク)に大きなゆがみをもたらすことはないでしょうか。 私たちは、子どもたちがみな、障害を持つ、持たないにかかわらず、それぞれに自立し、共に生きる生活を確保するために何をなすべきなのかを考えなければなりません。
詳しい内容および開催レポートはこちら  若草中学校区連携プロジェクト 若草中学校区連携プロジェクト地域の教育力の低下が問題となる中、地区の教育機関が子どもの長期的な発達に果たす役割の見直しが求められています。 本プロジェクトでは、就学移行や進学移行に伴う従来の個別の学校間連携を超え、 地区で共通の教育課題を明確化し、教育機関全体で取り組むような地区連携を試み、 地域教育の再生を支援を目指しています。 若草中学校区は公立の中学校1校、小学校3校、幼稚園3園、保育園1園などから成り、 本学もこの校区に位置しています。 校区は広く、多様な生活環境を背景にした子どもたちが一つの中学校に進学します。 本プロジェクトは、若草中学校区の小中の連携担当者の月例会議に参加し、 校区内連携の取り組みやそのあり方などを検討しました。 また、今年度は、校区別研修会において、校区共通の課題である「子ども自ら人間関係を主体的に築くには:地域の学校・園としての課題」について講演を行いました(8月1日)。 さらに平成19年度に引き続き、中学校1校、小学校1校の生活アンケートの分析を支援し、年度の変化や学年による違いなどその結果をそれぞれフィードバックしました。
 子どもの生活臨床 子どもの生活臨床児童養護施設等、子どもの福祉を担う入所型の施設では、入所児への心理的援助の必要性が叫ばれてきました。近年は、心理療法担当職員が配置されてきましたが、密室的な 心理療法をモデルとした旧来の心理的援助の有効性には限界があり、生活場面やコミュニティに開かれた生活臨床的な援助に期待が高まっています。 しかし、その具体的な実践方法は確立しておらず、個々の施設・職員の創意工夫に頼っているのが実情です。 そこで、本事業では、児童養護施設等から心理的援助のニーズや問題点、創意工夫を 調査し、それに対する効果的な対処と改善策を、本学大学院人間文化研究科附属心理 教育相談室との協力や施設職員向け研修会の開催によって図ることを目的としました。 施設の実情に根ざした心理的援助方法の開発によって、当該施設に貢献するのみならず、ひいては、こうした援助方法・およびその開発プロセスを、より広く社会に提言することを 目的としています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)2006-2011 Project of "KODOMO-gaku" in Faculty of Letters, Nara Women's University. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||