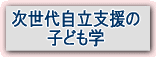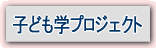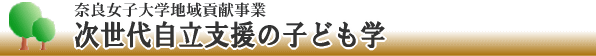
■平成19年度の企画
平成19年度に実施した企画で、すべて終了しています。
未来の社会のありようは次世代をになう子どもたちがどのように育つかにかかっています。
その子どもたちの育ちが種々の危機にさらされている今日、子どもにかかわる議論がさまざまな角度からなされなければなりません。
家庭・地域・学校において、子どもをめぐる問題がさまざまなかたちで起こっているいま、
子ども学はその解決の方途を探るあらたな実践学としての役割を求められています。
文学部「子ども学プロジェクト」は、子どもに関わる諸学を統合するとともに、子どもたちの育ちの現実に食い込むことのできる視座の獲得を目指しています。その核になっているのがこの地域貢献事業での実践・研究です。平成19年度度は、これまでの成果を踏まえて、以下の5つのプロジェクトを連動させ、あらたな展開を求めました。
【企画1】子どもの自立−生きるということ、働くということ−
今日の子育て観、学校観を問い直し、「子どもにおける自立」の意味を再定義します。
【企画2】若草中学校区連携プロジェクト
中学校区全体の教育機関の連携によって進められる子どもの発達支援を応援します。
【企画3】奈良の子育て環境と子どもの生活環境に関する調査研究
奈良における子育て環境と子どもの生活環境の現状とニーズを把握し、
新たな環境創出や支援に向けた提言を行います。
【企画4】若手教員問題解決支援「成長への一歩」
子どもの自立支援の担い手である若手教員のキャリア形成支援を行います。
【企画5】子どもヘルスプロモーション
子どもたちがおとなへと育つその連続のなかで、生活の基本となるべき健康と
その支援のあり方を、禁煙という切り口から見つめ、実践していきます。
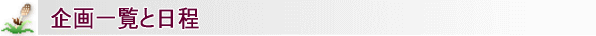

(企画1) |
奈良県、奈良市、大和郡山市
奈良市教育委員会、大和郡山市教育委員会、奈良女子大学附属学校部 |
 子どもの自立 子どもの自立
−生きるということ、働くということ−(公開連続講演会・一般)
大きな子ども、小さな子どもが群れ集い、守りつつ守られ、守られつつ守るという姿を見なくなりました。子どもがおとなに混じって働く姿もまた見なくなりました。こんな社会になったのは、長い人類の歴史のここわずか50年来のことです。人の育ちのありようとして、そこに大きなゆがみはないのでしょうか。いまあらためて「子どもが働く」ことの意味を考えます。
企画・進行: 浜田寿美男(文学部教授)
対象: 一般
教員、保育士、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
児童福祉関係者、子育て支援関係者、青少年育成関係者、大学院生ほか
|
日 時 |
場 所 |
テーマ |
| 第1回 |
2007年10月27日(日)
午後1時半〜4時 |
記念館2階講堂 |
働く若者たちの今 ― 労働市場の変化のなかで |
| 第2回 |
2007年11月17日(土)
午後1時半〜4時 |
文学部(総合研究棟)
北棟N202教室 |
働く前に身につけよう、返事、挨拶、生活習慣
― 自立支援の現場から |
| 第3回 |
2007年12月15日(土)
午後1時半〜4時 |
記念館2階講堂 |
体験学習があそびと学習と仕事を統合する
― きのくに子どもの村学園の「プロジェクト」の
ねらいと実際 |
| 第4回 |
2007年2月23日(土)
午後1時〜4時 |
講堂 |
新時代の大人化計画
― 若者たちの生活の情景を見つめて |
詳しい内容および開催レポートはこちら
 【Top】 【Top】
 若草中学校区連携プロジェクト 若草中学校区連携プロジェクト
地域の教育力の低下が問題となる中、地区の教育機関が子どもの長期的な発達に果たす役割の見直しが求められています。就学移行や進学移行に伴う校種間連携は全国各地で進められ、特定の学校間における移行期の学習形態やカリキュラム連携については先駆的実践が蓄積されつつあります。
本プロジェクトでは、そうした従来の個別の連携を超え、地区全体で共通の教育課題を明確化し、教育機関全体で取り組むような地区連携を試み、地域教育の再生を目指すものです。
若草中学校区は中学校1校、小学校3校、幼稚園3園、保育園2園などから成り、奈良女子大学もこの校区に位置しています。校区は広く、異なる生活環境にある子どもたちが一つの中学校に進学してきます。
このプロジェクトでは、若草中学校区を地区の単位として、研修やカンファランス、生活アンケートなどの実施を支援し、子どもの発達上の課題や地域独自の課題をみきわめ、校区の教育課題の明確化と整理を図り、新たな取り組みへの支援を行っていきます。個別の幼小連携や小中連携を含めた、地域全体の異校種間連携のデザインと実践の先駆けと位置づけています。
|
|
内 容
|
(1) 若草中学校区における研修会及び連携に関する助言等支援
(2) 生活アンケートの実施・分析支援 |
| 連 携 |
奈良市立若草中学校・鼓阪小学校・佐保小学校・鼓阪北小学校など |
報 告 |
◆校区別研修会に参加しました。
(8月10日(金)午前9時〜11時30分、於:若草中学校第1音楽室)
テーマ「聞くことの発達と校種間連携」(講師:奈良女子大学文学部准教授 本山方子)
◆夏休みに「若草太鼓」の練習に参加してきました。(7月30日〜8月24日までの4回)
・手作りの太鼓を大切に使っていました。とてもいい音が出ました。
・左右においた二つの太鼓をたたき分けるのは快感です。
◆若草中学校の文化祭を参観しました。(10月12日(金))
・オープニングは「若草太鼓」。大太鼓の勇壮な響きと、小太鼓の軽やかな鳴りが印象的です。
みなさんの熱心な練習の成果が伝わってきました。
・共同製作の作品や、学級で作り上げるダンスや演劇、ハンドベルの演奏など、
短い時間でしたが、楽しませていただきました。
◆’07鼓阪人権・文化フェスタを参観しました。(11月11日(日))
・保育園のみなさんの力強い「ゆりぐみ太鼓」が印象的でした。
・中学校のみなさんの「若草太鼓」は、文化祭の時よりもパワーアップして、たのもしい演奏でした。
・幼稚園や保育園、小学校、中学校の展示を拝見しました。素敵な作品がたくさんありました。
また、活発な活動の様子がよくわかりました。
|
その他 |
地域貢献事業以外に、平成19年度は若草中学校区の協力を得て、「子ども学プロジェクト」として
次の活動を行っています。
(1) 文学部人間行動科学科授業科目「子ども学インターンシップ実習」の実施
(2) 教職教育研究の実施
(3) その他: 学生・院生の教育支援経験の蓄積、 など
|
 【Top】 【Top】
 奈良の子育て環境と子どもの生活環境に関する調査研究 奈良の子育て環境と子どもの生活環境に関する調査研究
「奈良は子育てがしにくい」という声が県の内外から聞かれます。統計的にみても、合計特殊出生率が低い、共働き家庭の割合が少ない、20代女性の県外就業率が高いなどのデータがあります。県内で発生した子どもをめぐる事件もまだ記憶に新しいところです。
これまでとられてきた対策の中には、対症療法的なものにとどまり、実態とのずれを生じているものもあるかもしれません。地域のNPOなどによる取り組みは多く熱心になされていますが、自分たちの活動にどのような意義があるのか明確に把握できないまま、活動を続けていたり、熱心であるほど疲弊し、その結果、収束したりするケースも少なくありません。
こうした行き詰まりを乗り越え、新たな子育て支援・子ども支援のあり方を探るには、現状の正確な把握、それも広く浅い調査だけではなく、実態を深く知るためのミクロな調査が必要です。奈良NPOセンターと連携し、奈良県の子育ての現状について草の根の調査を行い、いま求められる支援のありようを検討し、提案します。
|
|
| 内 容 |
子育て環境・子どもが生きる環境の現状およびニーズに関する調査研究 |
| 対 象 |
奈良県下の子育てグループの実施者と利用者 |
| 報 告 |
◆草の根の調査の途中経過について、「みんなで子育て研修会」のシンポジウム「みんなでつくる地域の子育て(事例紹介とパネルトーク)」で報告しました。
報告では、少子化問題の難しさは、問題が社会的なものでありかつ個人的なものであること、支援策や制度とニーズとのギャップにあることを指摘しました。また、少子化対策のひとつとされている子育てと仕事の両立支援で求められているのは、使いやすい制度、選択肢(メニュー)があり、かつオープンにされていること、周囲の雰囲気および社会の空気、親同士のつながり、の4つであると述べて、生駒市のグループの事例を紹介しました。
|
| 連 携 |
奈良NPOセンター |
| 担当者 |
東村知子(文学部人間行動科学科助教) |
 【Top】 【Top】
 若手教員問題解決支援「成長への一歩」 若手教員問題解決支援「成長への一歩」  チラシ(PDF) チラシ(PDF)
「教師になる」ことは、子どもの自立支援の前線に立つことでもあります。
いきなり前線に立ったとき、さて何から手をつけたらよいのか、習熟を期待される課題が
目の前に山積されます。
授業実践に始まり、学級運営、様々な背景を抱えた子どもに応じた支援、校内分掌、職場の同僚関係の形成、保護者への説明と対応まで、課題は多様であり、まじめな教師ほど一人で思い悩む傾向にあります。
問題や困難は自らの成長の資源としていかに活かせるのか、また、自分の悩みや行き詰まり感は学校という場でいかにあり得ることなのか、教師の成長過程を展望し、問題解決の手がかりや足がかりを参加者のみなさんと一緒に考えていきます。
若手教員のほか、教員を志望する大学生にとってもキャリア形成の一助となる企画です。
|
|
| 日 時 |
2008年1月12日(土) 午後1時〜4時 |
| 場 所 |
奈良女子大学附属小学校 集会室 (近鉄奈良線学園前下車 北口 徒歩5分) |
| 対 象 |
初任期から教職歴数年程度の若手教員、教員志望の3回生以上の大学生
※小学校の事例が中心ですが、参加者の校種は問いません。 |
内 容 |
・現役教員の講話(学習指導や学級経営について、など)
日和佐尚・谷岡義高(奈良女子大学附属小学校教諭)
・若手教員による実践の報告と検討
羽山純子(奈良県葛城市立新庄小学校教諭)
・若手教員からの話
現在、困っていること、悩んでいること、やってみたいことなど
・教師の熟達と初任期の課題
本山方子(奈良女子大学文学部准教授)
・自由討論と交流
|
| 担当者 |
本山方子(文学部准教授) ・ 西村拓生(文学部准教授) ・ 藤原素子(文学部教授) |
※この企画は、奈良女子大学附属小学校と共同で行いました。
 【Top】 【Top】
以下は、保健管理センター(センター長:高橋裕子教授)が管轄・運営する企画です。
 子どもヘルスプロモーション 子どもヘルスプロモーション
平成15〜17年度の地域貢献特別支援事業において、「たばこ分野における健康なら21推進支援事業」として奈良県および奈良市とさまざまな事業を推進してきました。平成18年度は就学前後の喫煙防止教育教材配布と子どもタバコゼロプロジェクト(保健所、大学、医療関係者が禁煙教育・環境整備・喫煙者への禁煙支援の3つのヘルスプロモーションを軸とした総合的支援を提供し、子どもをタバコから守る地域力育成のためのプロジェクト)、未成年喫煙防止研究会を継続的に展開してきました。
平成19年度4月から奈良市においての学校敷地内禁煙化が実施され、それにともなう支援をおこなう予定です。今年度は、次の企画を展開していきます。
(1)就学前後の喫煙防止教育教材評価
(2)子どもたばこゼロプロジェクト
(3)第5回未成年喫煙防止研究会
(4)禁煙資料室の充実
詳しくは、こちらをご覧ください。
 【Top】 【Top】
 【HOME】 【HOME】
|
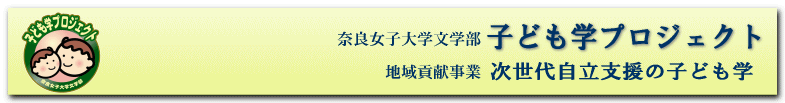
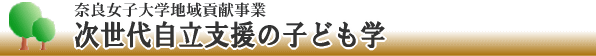
 子どもの自立
子どもの自立 若草中学校区連携プロジェクト
若草中学校区連携プロジェクト 奈良の子育て環境と子どもの生活環境に関する調査研究
奈良の子育て環境と子どもの生活環境に関する調査研究