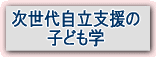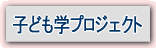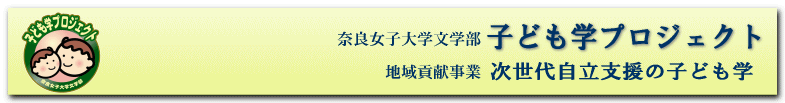 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
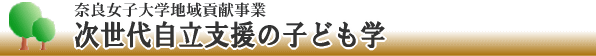 子ども学は、「子どもの生きる現場」から始まります。 未来の社会のありようは、 次世代をになう子どもたちがどのように生き、育つかにかかっています。 いま、その現場である家庭・地域・学校が大きく変容しつつあります。 この時代の変化の中で、子どもの自立はどのように果たされていくのか。 またそのために、おとなは何をしなければならないのか。 「次世代自立支援の子ども学」は、 以下の4つのプロジェクトを通して、みなさんとともにこの問題を考え、 支援のあり方を創出していきます。 【企画1】 公開連続講演会 「子どもたちの生活と表現活動――いま子どもたちの生きるかたち」 さまざまな領域の講師をお招きし、子どもたちの表現活動について考えていきます。 【企画2】 若草中学校区連携プロジェクト 中学校区の教育機関全体で、子どもの発達上の課題や地域独自の課題をみきわめ、 新たな取り組みを行うための支援を行います。 【企画3】 子どもの生活臨床 児童養護施設に育つ子ども等を対象とする、 生活場面やコミュニティに開かれた援助モデルを開発します。 【企画4】超低出生体重児の親の子育て支援 超低出生体重児の子どもを育てている親のピアカウンセリング活動を支援します。
 子どもたちの生活と表現活動 子どもたちの生活と表現活動――いま子どもたちの生きるかたち (公開連続講演会・一般) 詳しい内容及び開催レポートはこちら 人はみな、それぞれの生活の場で、自分を表現し、他者の表現を受けとめ、さらにはたがいの共同の表現を生み出しながら生きています。子どもたちもまた同じです。 個性はさまざまですが、誰もがそれぞれの個性に応じて、自らを表現し、それぞれの生きるかたちを作り出しています。そこでいう表現は、いわゆる音楽や絵画や文学という狭義の表現活動に限りません。学びや遊びもまた表現です。生活のかたちそのものが、子どもの一つの表現だともいえます。 今回の連続講演会では、このような観点から子どもたちの表現活動を再考します。 子どもたちはいま、学校の場で、あるいは生活の場で、自らを表現しえているのでしょうか。
 若草中学校区連携プロジェクト 若草中学校区連携プロジェクト地域の教育力の立て直しが問題となるなか、地区の教育機関が子どもの長期的な発達に果たす役割の見直しが求められています。 就学移行や進学移行に伴う校種間連携は全国各地で進められ、特定の校園間における移行期の学習形態やカリキュラム連携については先駆的実践が蓄積されつつあります。 これまでの2年間に引き続き、本プロジェクトは、従来の校種間連携を超え、子どもの育ちや教育に関する地区共通の課題を明確化し、教育機関全体で取り組むような地区連携を試み、地域教育の再生を目指します。 奈良市の若草中学校区は中学校1校、小学校3校、幼稚園3園、保育園2園、私立小・中学校1校から成り、本学もこの校区に位置しています。校区は広く、異なる個性をもつ子どもたちが一つの公立中学校に進学します。本プロジェクトでは、若草中学校区を地区の単位として、研修や子どもの生活アンケートの分析などを共にし、子どもの発達上の課題や地域独自の課題をみきわめ、校区の教育課題の明確化と整理を図り、新たな取り組みの支援を行います。
 子どもの生活臨床 子どもの生活臨床子どもに対する臨床的援助には、子どもの生活全体を見渡す広い視野が欠かせません。 その視野は、たとえば児童養護施設等に育つ子ども、あるいは、アルコール依存症の親を持つ機能不全の家庭に育つ子どもの臨床的援助には、ことさらに重要になります。 しかし、旧来の密室的な心理療法の援助モデルは、こうした対象への適用可能性に限界が指摘されてきました。そして近年は、生活場面やコミュニティに開かれた生活臨床的な援助モデルに期待が高まっています。しかし、その具体的な実践方法は確立しておらず、個々の施設・職員の創意工夫に頼っているのが実情です。 そこで本事業では、児童養護施設等の児童福祉施設や家庭支援団体から、心理的援助のニーズや問題点、創意工夫を調査し、それに対する効果的な対処と改善策を、大学院 人間文化研究科附属心理教育相談室との協力や施設職員向け研修会の開催によって図ることを目的としています。 子どもの生活臨床の実践的なモデル開発によって、当該施設・家族に貢献するのみならず こうした援助モデルとその開発プロセスを、より広く社会に発信することを目指しています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)2006-2011 Project of "KODOMO-gaku" in Faculty of Letters, Nara Women's University. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||